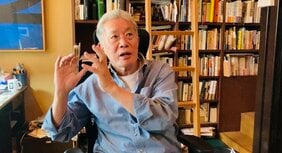意識的にアテンションを払うべきものは?
このアテンション・エコノミーの原理は、プラットフォーム企業側の収益獲得の最適化だけでなく、プラットフォームを利用するユーザー側の発信行動とも強く関係している。
SNSで投稿するユーザー自身、意識する/しないにかかわらず、いかにして他のユーザーのアテンションを集め、いかにして「バズる」かを競うようになっているのだ。
そしてSNSのアルゴリズムは、アテンションが集まるような人気コンテンツを優遇するロジックに最適化されているために、このようなユーザー間の競争に拍車をかけることになる。
また、アテンションが集まる人気コンテンツは一度アルゴリズム上で優遇されると、さらにアテンションを集めやすいという再帰的な構造をもっている。
たとえば、一定以上の「いいね」数を集めて人気のあるコンテンツ(=アテンションが集まっているコンテンツ)だとみなされれば、アルゴリズムはそれをより多くのユーザーの表示候補リストに含めるようになり、「おすすめ」などのタイムライン上に出現する頻度が上がる。
そうすると自然と多くのユーザーがその投稿に接触するようになるため、さらにそこに「いいね」などの反応が集まる、という循環が発生するのだ。そのときそのコンテンツが真実かどうかなどの信頼性や正確性はほとんど関係がなく、単に多くの人のアテンションを集められたかどうかが重要な指標になってしまう。
そこに他のユーザーのシステム1による直観的な判断(確証バイアスなどの偏った判断を含む)が重なることによって、ちょっとした投稿が予想外に拡散したり、誹謗中傷や炎上となって拡大したりする構造が構築されるわけだ。
SNSをはじめとするプラットフォームの情報に接する際は、直観的な反応に身を任せるのではなく、このようなアテンション・エコノミー環境におけるアルゴリズムを用いたメディアの特性と、認知バイアスなどの人間の心理特性にこそ、意識的なアテンションを払う必要があるといえるだろう。