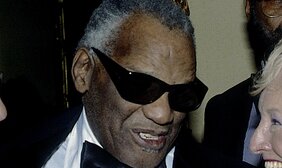たまたま問題提起され、じつにうまく引き継がれていった
昨年冬の議論では、11月15日の内閣官房・全世代型社会保障構築会議の際に、当初の予定になかった高額療養費制度が有識者委員によってたまたま問題提起され(当時の議事録には「本日の議題になっていない点で恐縮ですけれども、(中略)高額療養費制度の基準の見直しというものがあります」「高額療養費制度の在り方などについては、ぜひともスピード感を持って改革に取り組んでいただきたいと思います」という発言が記録されている)、その提案が翌週からの厚労省・社会保障審議会医療保険部会の議論にじつにうまく引き継がれていった、という経緯がある。
11月22日から4回にわたって行われたその医療保険部会の議論で、制度を利用する当事者の意見がまったく聴取されずに話が進んでいったのは、冒頭でも説明したとおりだ。
また、この医療保険部会の会議では、厚労省が有識者委員に自己負担上限額の具体的な値上げ金額を明らかにしていなかったことも、後に明らかになっている(その意味では、医療保険部会の有識者委員は厚労省に後出しじゃんけんをされた被害者といえなくもない)。
ともあれ、このような「議論」の出発点になったのが昨年11月の全世代型社会保障構築会議であったことを考えれば、今年6月にもこの会議で高額療養費制度について上記のような発言があったという事実には、充分に留意をしておいたほうがいいように思う。
そしてそもそも、「秋までに改めて方針を検討し、決定する」という政府の姿勢に現在も変化がない以上、高額療養費制度に関する議論(高額療養費制度の在り方に関する専門委員会)がこれから秋に向けていよいよ本格化してゆくことは確実だろう。
たとえ自分自身が今は利用していなくて他人ごとのように縁遠く感じるものであったとしても、その平穏な状況は明日いきなり反転して、高額療養費制度が必要になる状態に迫られてしまうかもしれない。その可能性は生きている以上誰にでもあって、自助努力だけでは回避することが不可能だ。
だからこそ、まさかのときの大きなリスクに備えるこの高額療養費制度は、誰にも遺漏なく利用できて安心できるものであることが望ましい。つまり、年齢収入、職業、居住地域等のいかんにかかわらず、全国民が当事者であるこの制度の議論は誰にとっても他人ごとではない、というわけだ。
今回の議論を、政府に都合の良い予定調和の結論にさせないためにも、また、現状でも多くの利用者を困らせている様々な制度的矛盾や課題を改善する方向へ踏み出してもらうためにも、今後の展開には常に注視を続け、新たな動きがあったときには可能な限り迅速に反応して、このような形で報告をしていきたい。
文/西村章