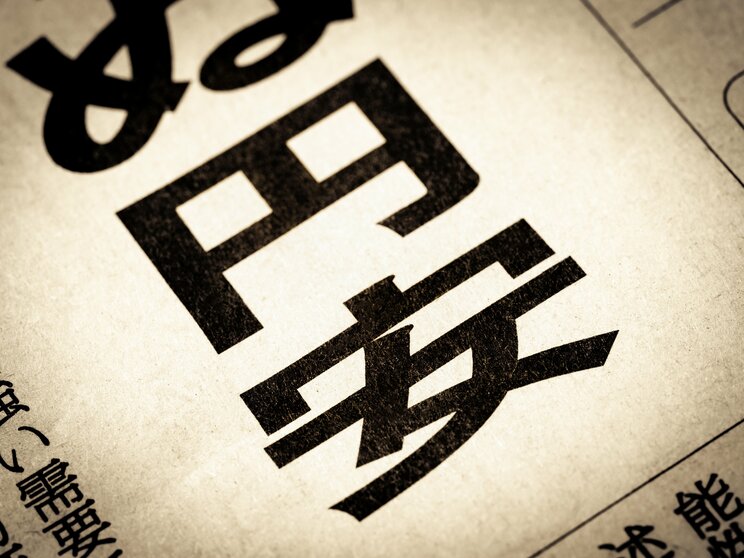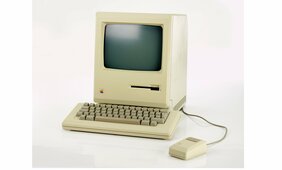日本から毎日、海外に巨額の支払いが発生している
唐鎌大輔(以下、唐鎌) 私は、2022年3月に円安局面が始まって以降、日米金利差だけではなく、もっと需給構造、端的には国際収支をもっと丁寧に分析すべきだと主張してきました。その際、特に大きな変化を強いられている項目として「サービス収支」、とりわけ「その他サービス収支」の赤字が急拡大していることに着目してきました。
ちなみに読者のために整理させていただくと、サービス収支は「旅行収支」、「輸送収支」、「その他サービス収支」の3項目から構成されています。輸送収支はあまり大きくなく、旅行収支は、いわゆるインバウンド黒字で猛烈に稼いでいます。
では、「その他サービス収支」とは何か。「その他」という曖昧な名称のせいで軽視されそうなので、私はこの赤字を「新時代の赤字」と呼んできました。
この赤字は「研究開発サービス」、「再保険サービス(次節『新たな円安要因と考えられる「外貨建て生命保険」とは』を参照)」、「コンサルティングサービス」など多様な取引で膨らんでいるのですが、最も大きいのが皆さんもよくご存じの「デジタル赤字」です。「新時代の赤字」のフレーズは流行らず、こちらは爆発的に流行りました(笑)。
河野龍太郎(以下、河野) たとえば、ネットフリックスやアマゾン・ミュージックのような動画や音楽の配信サービスを利用する人が増えていて、こうしたサブスクリプション(定額課金)サービスの利用料として、日本から毎日、海外に巨額の支払いが発生しているという話ですね。
唐鎌 その通りです。いわゆるGAFAMに代表される海外プラットフォーマーへの支払いを中心に構成されていますが、2015年に約▲2.6兆円だったものが、2024年は約▲6.8兆円に膨らんでいます。10年で倍以上です。
日本政府もマイクロソフトやグーグル、アマゾンといったプラットフォーマーとクラウド契約をしていますが、国民生活に目を向けても、ユーチューブやネットフリックスなどは娯楽上、欠かせない存在になりつつあります。iPhoneのクラウドストレージを契約している人も多いでしょう。もはや彼らのサービスは、日本の社会インフラの一部です。
しかし、そのインフラ利用料が、円ではなく外貨で支払われる状況になっているため、これらは円安相場の一因として注目せざるを得ないわけです。
なお、針小棒大に解釈する向きもあるので強調しておきたいのですが、あくまで「一因」であり、これが円安を直接的に引き起こしているとまで言うつもりはありません。ただ、このまま放置すれば、そうなる可能性は捨てきれないとは思っています。
河野 ならば、日本人がGAFAMのプラットフォーム上で画期的なコンテンツを作り、新たな付加価値を生み出すことができれば、デジタル赤字はそこまで問題にはならないはずだ、といった「根拠のない楽観論」が以前はありました。
現実にはデジタル赤字がどんどん膨らんでいるということは、日本が十分な付加価値を生み出せず、海外企業に支払う利用料ばかりが増えているということです。
なぜそんな話をしているかというと、近年、日本政府は企業にデジタル化を進めよと、ずっと旗を振ってきたのですが、結局、民間企業がデジタル化を進めれば進めるほど、海外への支払いが拡大し、デジタル赤字が膨らんでいくのではないか、そんな疑問をずっと持っていたからです。これについてはどうお考えですか。
唐鎌 その通りです。「デジタル赤字、それ自体が問題なのではない。それを活かして付加価値の高い財・サービスを生み出せばよいのだ」という意見はよく聞きますし、一見正論です。しかし、現実は厳しく、「単にコストが増えているだけ」という事実も真摯に受け止めたほうがよいと思います。
少なくとも、「プラットフォーマーのサービスを利用してお金を稼ぐ」という構図が続く限り、それは地主に地代を納め続ける小作人、さしずめ「デジタル小作人」と揶揄されるような状況と言わざるを得ません。
「デジタルサービスを活かして高付加価値を生み出す」は「豊かな小作人になろう」という文脈と理解できます。その考え方ももちろん必要だとは思いますが、敗北主義的な結論でもあります。もっと根本的な解決思想はないものでしょうか。