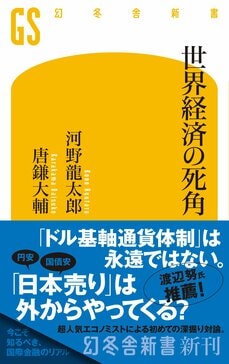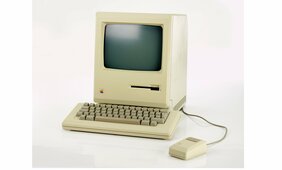デジタルサービスも原油などの天然資源に近い
河野 消費者保護といった問題だけでなく、独占がもたらす弊害という「市場の失敗」の側面もあるので、本来はGAFAMの本拠地のアメリカにおいても、政府が早くから公的に介入すべき問題だったと思います。独占力を持つ彼らは、実はイノベーションの阻害要因になっているということです。
ちなみに、貿易収支の黒字や赤字はよく話題になりますが、デジタルサービスは財と違って目に見えないため、「デジタル収支の赤字」が長い間、意識されなかったのでしょうか。
唐鎌 その潜在的な影響が認識されていなかったわけではないと思います。2022年7月に行われた経済産業省の「半導体・デジタル産業戦略検討会議」の資料を見ると、クラウドサービスへの支払いから構成されるコンピューターサービス赤字に関し、2030年までには原油輸入に匹敵するとの試算が紹介されています。
原油と比較することは、秀逸だと私は感じました。「経済活動に必要不可欠だが、相手に価格決定権がある」という意味では、デジタルサービスも天然資源に近い種類の生産要素だと私は考えています。
当然、原油価格の上昇は企業の生産コストを押し上げるため、利益を圧迫する要因になります。GAFAMなどが提供するデジタルサービスも、これと同じではないかと思います。
GAFAMで働く人たちの賃金は上がり続けているわけですから、彼らが提供するサービスの利用料は、今後も値上がりが予想されます。
それでも「デジタル赤字それ自体が問題なのではない。それを活かして付加価値の高い財・サービスを生み出せばよいのだ」との主張を繰り返すのでしょうか。私は、ややナイーブすぎるのではないかと感じます。
河野 “デジタルサービスも天然資源に近い種類の生産要素”というのは、極めて重要な指摘ですね。
国際収支で見て、デジタル赤字は、今後どのくらい増えると予想しておけばいいですか。為替レートの基調にも影響するでしょうから、ぜひお聞きしたいと思います。
唐鎌 難しいところですが、簡単な試算はあります。たとえば、前出の経済産業省の会議では、デジタル赤字の一部でしかないコンピューターサービス赤字について「2030年までに▲8兆円」という試算でした。他のデジタル赤字と合わせれば優に▲10兆円を超えてくるでしょう。
2024年の輸入金額を商品別に見ますと、液化天然ガス(LNG)で▲6.2兆円、原油が▲10.7兆円でしたので、その試算が正しければ、2030年にはデジタル赤字が主要な天然資源の輸入額を凌駕してきそうです。
ちなみにデジタル赤字全体という意味では、2022年から2024年の増加ペースが年平均して+16%程度でした。もし、このペースで2030年まで伸び続けると、デジタル赤字は▲15兆円を優に超えます。
ある程度の幅を持って見たとしても、非常にラフな言い方ですが、「2030年にはデジタル赤字だけで優に▲10兆円以上」というのが一つの目線ではないかと思っています。
河野 とはいえサービス収支全体で見れば、旅行収支黒字で、全部とは言いませんが、デジタル赤字をかなり相殺できていますよね。
唐鎌 たしかにサービス収支には、旅行収支という稼ぎ頭もあります。これは2024年、約+6.1兆円と過去最大の黒字を記録しました。その結果、サービス収支全体の赤字は、まだ抑制されています。
しかし、人手不足が極まる日本の状況を踏まえると、労働集約的な観光産業だけで外貨を獲得し続ける戦略は、持続可能とは言えないでしょう。
「デジタル赤字は増え続ける一方、旅行収支黒字はピークアウトが近い。結果的にサービス収支赤字は拡大基調に入る」というのが、基本シナリオではないかと思います。
河野 資源配分の話なので、収支の赤字、黒字そのものが問題ではないのですが、だとすると、やはりドル円相場に大きな影響を与えると考えてよさそうですね。
唐鎌 私はそう考えています。非常に長い目で見れば、サービス収支赤字だけで▲10兆円の大台が定着する時代も視野に入ると思っています。
ちなみに貿易・サービス収支の赤字が▲10兆円を超えたことは、歴史上3回しかありません。2013年、2014年、2022年です。いずれも円の対ドル相場が2桁以上の下落率を記録した年です。その因果はここで詳しく議論はしませんが、無関係のはずはないでしょう。
加えて、それら3回の大きな赤字は、すべて貿易収支の赤字にけん引されたものでした。それが、サービス収支の赤字にけん引される時代に変わっていく可能性はあると思います。
文/河野龍太郎、唐鎌大輔