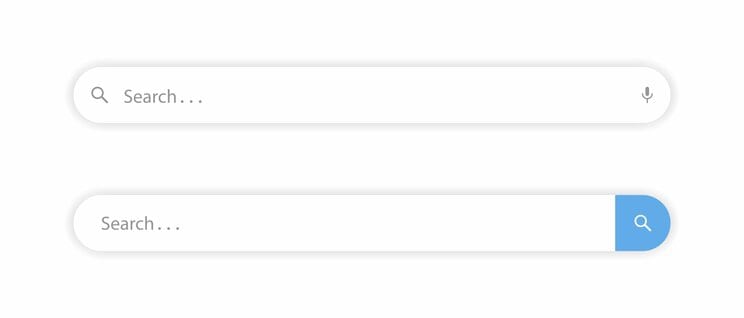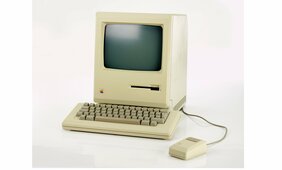本来許されてはいけなかったビジネスモデル
河野 「デジタル小作人化」しているという意見に私も同感です。GAFAMなどの巨大IT企業の収益の源泉は、彼らが持っている膨大なデータですが、そのデータを提供しているのは、実は私たち利用者です。
私たちは、GAFAMのプラットフォームを利用し、せっせと喜んでデータを提供しているわけですが、そのデータが生み出す付加価値は持っていかれ、利用料ばかり支払っているのが現状です。
「デジタル小作人化」、いや「デジタル農奴化」と言うべきかもしれませんが、この問題は日本だけではなく、世界的な課題です。ただ日本では、この問題を指摘する声が、つい最近まで少なかったのが特徴的です。『成長の臨界』でも、この問題にフォーカスを当てました。
私たちは無料の検索や無料のメールを、当然のように喜んで使っています。しかし、そもそもこのようなビジネスモデルは、本来許されてはいけなかったのです。
「ただ」だと思って利用しているうちに、我々の個人データは知らぬ間に収集・流用され、ビジネスに活用されています。そして気がつけば、私たちはその仕組みにがんじがらめになり、抜け出せなくなっているのです。もしお金を払わずに済んでいるのだとしたら、それは私たちが「顧客」ではなく、「売られる商品」になっているということですかね。
他の業界では、このようなビジネスモデルは決して容認されていません。たとえば、弁護士や医師が「弁護費用や診療費は無料でいい。その代わり、あなたの個人情報を他のビジネスで自由に使います」と言ったらどうでしょうか?
そんな契約は法的に絶対に許されないはずです。それなのに、なぜかGAFAMのような巨大テック企業には、こうした行為が長らく黙認されてきたのです。この問題については、ユヴァル・ノア・ハラリが新著『NEXUS』(河出書房新社、2025年刊)で詳しく論じています。
その点、EUは早くからGAFAMによる「搾取」のリスクをきちんと議論し、規制を進めてきました。
一方の日本はというと、GAFAMなどの巨大テック企業の経営者の言うことを無批判に信じ、自分たちが「デジタル農奴化」していることに気がついていません。AI企業のトップが来日すると、日本では単純に歓迎ムードになって、首相官邸に招いたりするのですが、事態をもっと深刻に捉える必要があります。
唐鎌 まったく同感です。日本社会ではどことなく、資本主義ゆえに「ウィナー・テイクス・オール(Winner takes all/勝者総取り)」は仕方ないという、妙な物わかりのよさがあるように思います。
すでに世界は、市場機能を万能とする新自由主義的な考え方を離れ、いかに政府が民間の経済活動に介入し、自国を勝たせるかという視点を持ち始めていると思います。そのあたりの危機意識は、日本はまだ薄いのかもしれません。
たとえば、iPhoneでアプリをダウンロードすると、まずアップルが料金を受け取り、その後、アプリの開発者に収益が配分されます。この際、アップルが約3割の手数料を差し引いているのですが、これが「高すぎるのではないか」と問題視され、EUはこの部分への課税を提案しました。こうした新たな税制がEUのスタンダードになった場合、日本も同様の課税措置を検討するのか。
第二次トランプ政権発足以降は関税交渉の行方も考慮しなければならず、先行きを検討するのは難しくなってしまいましたが、プラットフォーマーに対するEUの姿勢からは、日本が学べる部分もあるのではないかと思っています。
日本は搾取されているという意識が希薄なまま、妙な納得感を持ってしまっているように思います。もっと早くから声を上げておくべきだったと思いますが、これから声を上げるとなると、トランプ政権に対抗する構図になるのが悩ましいところです。