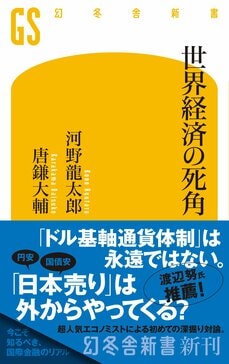不動産価格はこのまま上がり続けるのか
河野 これまでもお話ししたように、日本人の賃金はこの30年間、名目でも実質でもまったく上がっていません。最近、賃金が上がり始めたといっても、物価高にまったく追いついていませんから、実質賃金はむしろ目減りしています。それでも近年、不動産価格は大きく上昇しているので、日本人の感覚では「割高」に感じてしまうと思います。
一方で、海外の人たちは毎年数%ずつ賃金が上がり続けているため、彼らから見れば、日本の資産は“割安”に見えます。毎年2%の上昇でも、25年間続けば、所得は1.7倍に膨らみます。所得が2倍近くに膨らんだ海外の人たちから見れば、日本の不動産価格は相当に割安です。外国人が抱く割安感は、最近の円安によってさらに強調されているけれど、本質的な要因は、日本の賃金と物価が長期間、上昇しなかったことにあると私は考えています。
ここ数年の円安は、コロナ後のインフレに対して、アメリカやヨーロッパが利上げを続ける一方で、日本が金融緩和を続けたために加速しました。でも、それは一時的な話で、本質的には、過去四半世紀の賃金の停滞、そしてその次に起こった物価の停滞が大きいということです。
唐鎌 それは、いわゆる円の実質実効為替レートについて「半世紀ぶりの円安」と言われる現象ですね。名目為替レートの格差もさることながら、物価の格差も加味した実質為替レートで見ると、さらに円の価値が劣化しているという話です。
河野 そうです。過去四半世紀、日本では時間当たり生産性は3割も上がっているのに、賃金はまったく上がりませんでした。時間当たり実質賃金は、横ばいのままです。
国内の売上が増えないため、2010年代の初頭までは、株式市場も低迷が続いていましたが、過去10年ほどは海外の儲けを反映する形で、株価も上昇しています。
これは企業努力と言えなくもないのですが、実際には生産性が向上しているにもかかわらず賃金が抑えられている結果、働く人々が犠牲となって企業の業績がより大きく改善し、それに伴って株価も上がっているということだと思います。
一方で、不動産市場は世界的に価格が上がっているのに、日本だけが取り残されていました。その結果、海外の人から見ると相当に“割安”だから、ここにきて購入の動きが強まっている。欧米の都市部に比べて、日本の都市部の不動産価格が低いという話だけではありません。
興味深いのは、アジア諸国の都市よりも、東京の不動産のほうがはるかに安くなっている、という現実です。これでは日本人が都心の物件を買えなくなるのも当然で、サラリーマンが自力で住宅を持つのは、ますます難しくなってしまう。もちろん、今回のインフレをきっかけに、賃金が上がるメカニズムが回り始めれば、少しは日本人も購入しやすくなるかもしれません。
中国の人たちは、中国内から外に資本を持ち出すのに一苦労しますが、エリート層は、いろいろなツールを駆使して、日本の不動産を買い続けるでしょうね。
唐鎌 株・債券・為替といった伝統的な金融市場に限らず、新築マンションに代表される不動産市場でも海外マネーの流入が進むことで、日本人の生活実感を離れて価格形成が起きていますよね。日本経済が外部要因に対して脆弱になっている状況を実感します。
河野 ただ、念のために言っておくと、中国の人たちは必ずしも共産党体制の崩壊といったリスクを強く意識しているわけではなさそうです。あくまで、国際分散投資の一環という感じですね。
日本の「パワーカップル」が高額物件を買っているということの背景にも触れておきましょう。日本人の賃金が上がらなかったもう一つの要因として、労働市場の大きな変化がありました。たとえば、女性の労働参加が進み、労働市場全体の需給バランスが変わりましたが、男性と同じように優秀な労働力の供給が増えたから、男性の賃金が上がらなくなったという点も無視できません。
家庭単位で見ると、共働きが増えることで世帯収入は増えているわけで、パワーカップルであれば、都心のマンションの購入も可能です。
かつては、労働経済学で広く知られる「ダグラス=有沢の法則」に見られるように、賃金の高い労働者の配偶者は家庭に入り、賃金の低い労働者の配偶者は外で働くという傾向がありました。こうした働き方の違いがあったために、賃金格差は、婚姻によって自然と緩和される傾向にあったのです。これは世界的な現象でした。
しかし、現在では、この法則はすっかり崩れ、世界的に「同類婚」が一般的になっています。高い教育を受けた人は同じく高学歴の人と、低学歴の人は同様の背景を持つ人と結婚する傾向が強まっており、その結果、婚姻によってむしろ経済的な格差が拡大するようになっています。
唐鎌 最近では住宅ローンの年限を40年や50年にする動きも出てきていますよね。今まで一人で借りていたものが2人で借りるようになり、今度は2人で借りながら期間も長期化する、という流れに入っているように見えます。
河野 50年ローンとはかなり長いですが、本当にそういう動きが起こっているんですか。
唐鎌 そのようです。今でも35年ローンが主流だとは思いますが、最近は40年や50年ローンという商品も目にするようになっています。
河野 なるほど。長寿化が進んでいるので、当然の流れなのですかね。働く期間が延びれば、ローンの年限も長くなりますし。
唐鎌 はい。マクロ的には不動産購入の原資が膨らむ話ではありますから、日銀による少々の利上げが行われたとしても、不動産価格は大きく下落することなく、当面は下支えされそうですね。結局、国内外の様々な要因が、不動産価格の押し上げに寄与している現状を意識せざるを得ません。
文/河野龍太郎、唐鎌大輔