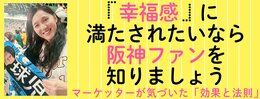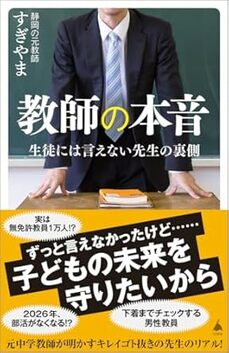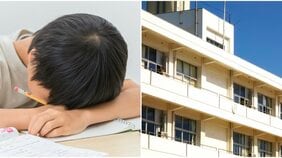先生は減っても行事は減らない
教員不足の現状に輪をかけて、現場の教員を苦しめているのが業務量の多さ。もうとにかく、とにかく忙しい! 働けど働けど仕事が終わらないぐらい、過重労働なのです。
教員が全然足りていないのに、業務量はまったく減らない。だから、一人の教師が抱える仕事は逆にドンドン増えているのです。
なぜそうなるかというと、新しい施策が毎年増えていく一方で、減ることは少ないから。「去年までやっていたことは、今年も当然やる」というのが、教育現場の基本スタンスなのです。
民間企業の場合、経営者が常にコスト削減に目を光らせているため、無駄な業務はドンドン削られていきます。
しかし、学校というのは毎年新しい行事、新しい業務が増えていきます。意味があるのかないのかわからない業務も含めて、です。せめて毎年、ゼロベースで見直ししてくれればいいんですが、やめるかどうかの検討はほとんど行われません。
学校や行政というのは、新しいことを始めるのは得意なんですが、逆にやめるのはとても苦手なんです。補助金を思い浮かべてもらえるとわかりやすいと思うんですが、新しく始めたらみんな喜びます。でも今までもらえていた補助金が急に打ち切られたら、たぶんクレームが殺到しますよね?
学校も同じ。たとえば、去年までやっていた行事をやめるのはとても難しいのです。やめようとすると、生徒や保護者、場合によっては地域住民からも猛反対に遭うから。
たとえば、それまで毎年やっていたマラソン大会を「今年からやめます」と言うと、
「去年までやっていたのになんで!?」「うちの子はマラソン大会しか楽しみがなかったのに」「◯◯中の伝統を潰す気か!?」……などと、生徒や保護者からものすごいクレームが殺到します。
たとえ最初は、誰かが思いつきで始めたような企画や行事でもそう。2〜3年もやっていると、いつの間にか『伝統』になってしまう。それでやめるにやめられなくなってしまった……。「誰がこんなこと始めたんだ!?」なんてことがよくあるんです。
もちろんマラソン大会というのは一例。
行事やイベントなんて、今みたいに少子化が進んで先生も減ったら、昔と同じようにはできない。そんなのちょっと考えたらわかりそうなもんですよね?
ところが、生徒や保護者から「なくなるのは寂しい」「楽しみにしていた子どもがかわいそう」と言われてしまうと、先生としては無慈悲に無くしてしまうのは心苦しくなります。これはもう感情の話なので、理屈ではないんですね。
写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock