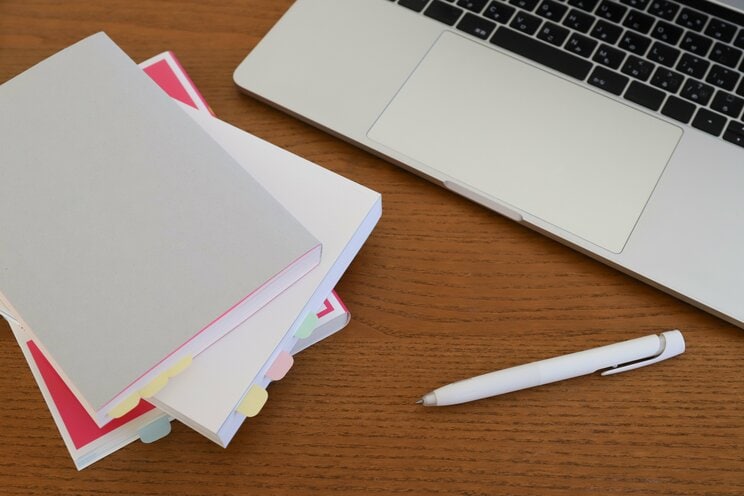タブレットを活用した「デジタル教科書」の大きな課題
全国各地の教育現場で導入が進む「デジタル教科書」。紙の教科書と同じ内容のものがPCやタブレット端末などに入っており、2019年から紙の教科書の「代替教材」として学校での使用が認められている。
文部科学相の諮問機関である中央教育審議会デジタル教科書推進ワーキンググループ(作業部会)は、今年2月に中間まとめ案を策定。これによると、デジタル教科書は2030年度から「正式な教科書」として導入される見通しで、紙の教科書と同様、検定や無償配布の対象となるようだ。
また導入形式は、「紙のみ」「デジタルのみ」、そして一部を紙、残りをデジタルとする「ハイブリッド」の3種類ある。各自治体の教育委員会が、いずれか1つを選択できるようになる予定だ。
昨年度からは、小学5年生から中学3年生を対象に、英語や算数・数学の授業でデジタル教科書の本格的な活用が始まっている。
そこで今回、現役の教諭たちに、デジタル教科書の実情や本音を聞いてみた。まず兵庫県の公立小学校に勤務するAさん(30代・男性教諭)は、現場の問題をこう語る。
「最大の問題は、タブレットが故障すると、すぐに教材を見られなくなることです。その影響で、授業についてこられなくなる児童が出てくることもあります。実際に、授業中に複数の児童のタブレットが同時に故障し、その対応に追われて授業が思うように進まなかったこともありました。
あと、階段などでタブレットを落として、液晶をバキバキに割ってしまうケースも少なくありません。今の学校では、通常使用の範囲内であれば、修理費用は学校や自治体が負担しています。ただし、故意や重大な過失による破損の場合には、保護者が負担するケースもあるため、事前に教員や保護者にしっかり説明しておかなければなりません。
また、端末によっては操作が難しく、特に低学年の児童にはなかなか定着しづらいのが現状です。さらに、タブレットには子どもたちの集中力を削ぐ要素も多く、授業中に写真を撮って遊ぶ児童も多い。
何度注意してもやめない場合は、タブレットを没収するという学年ごとのルールもあります。しかし、2030年度からデジタル教科書が『正式な教科書』になると、同じ対応を取ってよいのか……。ちょっと不安に感じています」(Aさん)