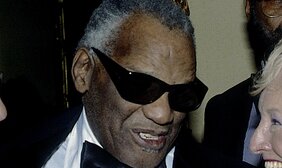不登校の原因は「いじめ」とは限らない
不登校は今、大きな社会問題になっています。
2024年10月末、34万人以上の小・中学生が不登校という調査結果が発表され、新聞などでも大きな話題となりました(文部科学省『令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要』)。
去年はおよそ29万人で大騒ぎしていたのに、あっという間に30万人超え。ただし、この34万人というのは『年間30日間以上欠席』の生徒だけで、それだけいるということ。不登校というのは「来るか?」「来ないか?」と、簡単に割り切れるような問題ではなく、来たり来なかったり、休みがちだったりする子の方が圧倒的に多いのです。
29日欠席の子や、別室登校の子、毎日午前中は来られない子などは、ここに含まれていません。だから、私は、実際はこの3倍以上は『ほぼ不登校』の生徒がいると考えています。
不登校の子どもは、この11年間ずっと増え続けていています。34万人というと不登校(30日以上欠席者)の調査・統計の始まった1991年から30年余りで5倍以上です。
特に2020年度以降、一気に15万人も増えています。それくらい急増しているのです。
これはおそらく、今まで「学校行かないと困る」と思っていた子どもたちが、コロナをきっかけに「あれ、意外と学校行かなくても困らないじゃん」と感じてしまったからだと私は思っています。
コロナ禍を機に「リモートワークでも意外と大丈夫だ」と気づき、そのまま週の半分は在宅になったというようなサラリーマンがたくさんいますが、要はそれと同じことです。
子どもが不登校になると、親や先生は必死に原因を探します。
「友だちにいじめられたのか?」
「担任の先生と合わないの?」
「授業についていけていない?」
などと問い詰め、必ず何か原因があって不登校になっているんだろう、と思ってしまいがちです。
しかし私が経験したケースでは「明確な原因なんて結局わからない」というのがほとんどでした。そりゃそうです。