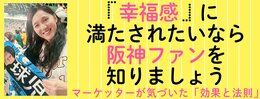学校教育でLGBTQは想定されていない
LGBTQに関するニュースを毎日のように目にするようになりました。
ジェンダーフリートイレ、同性婚、パートナーシップ制度などなど。学校でもLGBTQに関する問題は見過ごせないものになりつつあります。
簡単に解説すると、LGBTQとはレズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシャル(両性愛者)、トランスジェンダー(性別違和、性同一性障害)、クエスチョニング(その他)など、性的マイノリティの総称。
著者である私はゲイ(男性同性愛者)で、YouTubeなどでもカミングアウトしています。「ゲイになるのに何かキッカケがあったんですか?」とよく訊かれるのですが、LGBTQは多くの場合は、先天的なものです。
今も昔も、人口の約10%の割合で必ず存在すると言われています。これは左利きと同じぐらいの割合です。
1学年100人いたら、10人ほどは必ずそういう生徒がいるのです。1クラスでいうと2〜4人は必ずいます。
つまり、学校現場では「どのクラスにも必ずそういう子がいる」という前提で、教育活動をしていく必要があるということ。
ところが、学校教育においてはまだ根本のレベルからして、LGBTQ対応やジェンダー教育が進んでいないのが現状です。
まず、教育活動の大本である『学習指導要領』にLGBTQに関する記載がありません。そこに載っていないということは、学校では、基本的にLGBTQ教育は行わないということです。学習指導要領は、まだ『男女平等』の実現を謳っているレベルです。
現在の学校教育では、LGBTQの存在はそもそも想定されていないのです。
これには政治的な背景もあります。保守層は夫婦別姓反対、同性婚反対、LGBT理解増進法反対を主張する人が多いからです。その是非についてはここでは論じませんが、ひとつだけ理解してほしいのは、良い悪いに関わらずLGBTQは存在するということ。
あなたの隣の席の子がそうだったかもしれないし、今のあなたの部下もそうかもしれません。あなたのお子さんがゲイという可能性だって大いにあるのです。「私の周りにはそんな人いない」と言う人もいますが、『いない』のではなく、『言えていない』だけ。
LGBTQは一部の特異な人ではなく、常にあなたの目の前にいる人たちなのです。