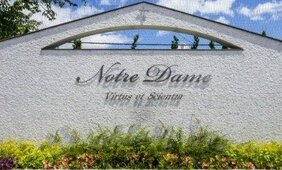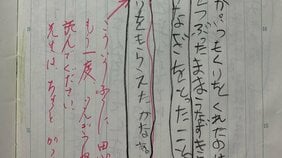議論の肝は教員の待遇改善ではない
――現在の国会では給持法についても審議されています。
給特法(注:「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称、1972年に成立)の改正ですね。これは今まさに、衆議院で可決され、参議院での審議が始まろうとしている話です。
教員は「給特法」によって、基本給の4%にあたる「教職調整額」が支払われています。しかし、この法律によって教員には残業代が支払われないため、「定額働かせ放題」じゃないか、という批判があがっていて、今回の議論もそれを受けたものです。
もともと、給特法改正の一番の後押しになったのは、「このままでは現場がもたない」という、長時間過密労働に苦しむ現場の教員たちの声でした。
しかし、いつの間にか議論の核が「教員の待遇改善」へとすり替わってしまった。教職調整額を4%から何パーセントまで引き上げれば良いのか、という話に焦点が向いています。
残業代の代わりに支給される教職調整額を、例えば10%まで引き上げたら、教員の待遇は根本的に改善し、長時間労働がなくなるのか…。そんなわけがありません。
大阪大の髙橋哲准教授が着目しているように、そもそも、給特法は教員の残業時間を減らすことを目的につくられた法律です。ならば、問うべきは「なぜそれが機能しなかったのか」であるはずなのに、その本質の部分が議論されていないんですよね。