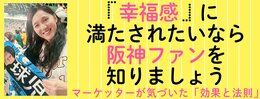不登校の理由はわからないことが多い
「わたくしは、こうこうこういう理由で不登校になりました」なんて、スラスラと言語化できるぐらいだったら不登校にはならないでしょう。そういう言葉にできないモヤモヤや、積み重なったよくわからないストレスとかがあって、自分でもそれを処理できなくて不登校になるのです。
数学のように、原因はコレだ! とスパッと割り切れるような問題じゃないんです。「なんで行けないのか?」を生徒本人も説明できないし、本人もわからない。そういうケースが一番多いのです。
私の体感では、不登校になる生徒は『心のエネルギー』のようなものが枯渇している子が多い、と感じています。話していても、家での様子を聞いても、どうもボーッとしがちで、心のエネルギー=活力、生きる原動力がほとんどないように感じるのです。外に出ると活発な子でも、すぐにエネルギー切れになってしまう。
そういう子にとって不登校期間は、心のエネルギーを充電するために必要な期間、と考えることもできるかもしれません。
もちろん、昔も心のエネルギーが空になってしまう子はたくさんいたと思います。でも、昔は親や学校に強制力があったため、それでも無理矢理学校に行かされていることが多かっただけ。
ところが今は家庭環境が複雑だったり、発達障害だったり、いろいろな背景を抱えている子が多いです。そのせいで、普通はご飯を食べて一晩寝れば充電できるエネルギーが、うまく充電できないままになってしまい、それが一定のラインを越えると不登校になっていくのではないかと、私はそう考えています。
そして、心のエネルギーの量と、その充電に必要な時間には、個人差があります。生まれつきエネルギーのキャパシティが大きい子もいれば、もともと小さくて、充電に時間がかかる子もいるのです。
中には普段は元気なのに、学校のことを考えると急に不安になって、一気にエネルギーがゼロになってしまうような子もいます。
だから、「学校が悪い」「親が悪い」「友だちが悪い」と無理矢理原因を探そうとするよりも、どうやったらその子の心のエネルギーを充足させてあげられるか?を考える方が建設的です。