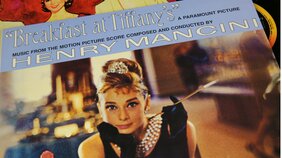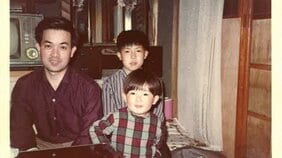グルメ
会員限定記事
ナポリタンは「劣った偽物」でもなければ「賞賛すべきノスタルジー」でもない…料理における権威主義と決別した平野紗季子というヒーロー
パスタの偽物として不当な評価を受けたかと思えば、懐かしのメニューとして崇められたりもするスパゲティ・ナポリタン。そんなナポリタンをそのどちらでもなく単に好きになれないと言い切ったのがフードエッセイストの平野紗季子さんだ。なるほど確かに料理における権威主義的な考え方は世の中に明らかに存在する。
料理人・文筆家の稲田俊輔が上梓した新書『食の本 ある料理人の読書録』より一部抜粋・再構成し、平野紗季子の清々しいほどに美味しいものを愛し評する素晴らしさを解説する。
食の本 ある料理人の読書録 #2
この記事は会員限定記事(無料) です
続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
次のページ
「平野紗季子という事件」
関連記事
-
-
-
-
大正時代に建てられた長谷の和モダン建築で味わう研ぎ澄まされた蕎麦と香り豊かなコーヒー〜鎌倉 北橋鎌倉だから、おいしい 第二章 #17
-
-
会員限定記事(無料)
-
「一流」とされる組織ほど内向き「論理的に相手を説得できる人材」より「空気を読んで、円満な人間関係を築ける人材」を重視する奇妙な日本企業日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったのか #5
-
-
「1人の女子生徒が突然、バッタリと倒れた」誰も助けようとしなかった甲子園の開会式…日本人の多くが「何もしないほうが得」と考えている危険日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったのか #4
-
-
-