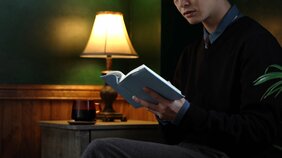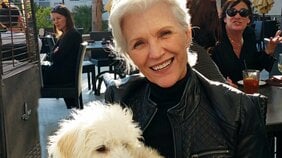「すみません」を「ありがとう」に換えると、世間が優しくなる
日本人は、「ありがとう」と言えばいいところを「すみません」と言う。外国語を習っていると、そう感じることがある。
たとえば、レストランが混んでいて待たされたとき、日本の店員さんは「お待たせしてすみません」と謝ってくれる。英語なら「Thank you for waiting」(待ってくれて、ありがとう)なのに。
混んでいるのも、客が予約せずに行ったのも、店のせいじゃないのに、謝ったとたんに、なんとなく自分の不手際のような気がして、店員さんの気が滅入るのではないかしら。一方、「待ってくださって、ありがとうございます」なら、同じ行列も「入れなくても待ってくれるお店のファンの列」に見えてくるはず。
客のほうも、「すみません」と言われると「早くしてね」と言いたくなるところを、「ありがとう」と言われると「自分の意思で待っていること」を再確認して「気にしないで」と言ってあげたくなるのでは?
「ありがとう」が言える店員さんのほうが前向きでいられるうえに、カスタマーハラスメントに遭いにくい気がする。
親切にしてもらったときも「すみません」と言う人が多い。「見ず知らずの人に、お手を煩わせてすみません」という謙虚な気持ちは美しいけれど、そんなふうにして生きていると、意識の真ん中に「人様の手を煩わすなんてダメ人間」という核のようなものができてしまうような気がする。そうしたら、大事なときに、人前で萎縮したり緊張したりしてしまわない?
そして、他人が「人様を煩わす行為」をしたとき、自分が自制している反動で、憤りを感じたり、イライラしたりもするのではないだろうか。「すみません」で暮らしていると、世間が生きづらく、厳しいところに感じてくるはず。だから私は、謙虚過ぎる人がいつも心配になる。世間は温かいもの、助け合うもの、そう思っていたら、俄然生きやすくなる。
子育て中の短縮業務で定時より早く退勤するにあたって、本当に申し訳なさそうに「すみません、すみません」と言いつつ席を立つのもいかがなものかと私は思う。悪いこともしていないのに謝っていると、なんだか情けない気持ちになって、仕事も子育ても楽しめなくなってしまう。それでは、モチベーションも自己肯定感も下がって、あまりにももったいないので、私が上司なら、こういう「すみません」は禁止したいくらいだ。
とはいえ、職種によっては、やはり残ったメンバーにしわ寄せが行くこともあるはず。それなのに、何も言わずに、まるで定時退社のように帰られた日には、今度は周囲がイラついてモチベーションが下がるので、そこは「ありがとう」でカバーしよう。「お先に帰ります。(いつも支えてくださって)ありがとうございます」なら、言われたほうもそんなに悪い気はしないのでは?