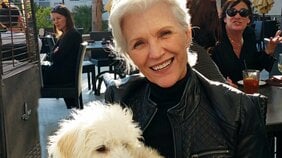都心での運用上の課題
「最も大きなメリットは、施設へのアクセシビリティの向上です。利便性のある場所に設立されることで、ニーズがありつつも施設が遠いために利用できなかった未成年や経済的に困窮している女性たちが利用しやすくなることが期待できます」
熊本の慈恵病院では運用開始から昨年3月末までの17年間で、179人の子どもが預けられ、このうち29人の子どもが関東地方在住の人によって預けられたことが分かっている。一方、アクセス面の向上により、懸念点も想定されている。
「事業規模を超える利用者拡大の可能性があり、東京のような人口の多い地域で利用者の匿名性を担保する運用は、地方よりも配慮が必要となるでしょう」
「賛育会病院」のベビーバスケットに近い出入り口には、場所を知らせるための緑のランプが常時、点灯しているが、夜間も人通りが多い都心部にあるため、SNSなどによって個人が特定されるトラブルにつながりかねないなど、懸念の声もあがっている。
実際に、先駆者である熊本の慈恵病院は開設後、運営上でどのような課題に直面したのか。
「最も大きな課題は、『赤ちゃんポスト』『内密出産』が、ニーズがあり、非常に公共性が高く、母子の生存に関わる取り組みであるにもかかわらず、いち医療法人に個人情報の取り扱いや費用負担を委ねているという点です」
本来は公的な支援で対応するべき取り組みを、民間が「緊急避難」として応じている状況のため、法律や行政に関わる課題の面で困難が生じているという。
「親の匿名性を守る一方で、子ども自身が自らの“出自を知る権利”がどこまで保障されるのかが課題となっています。法務省の『内密出産のガイドライン』で個人情報の開示が前提とされていますが、赤ちゃんポストを利用する緊急時の妊婦には困難であることから、慈恵病院と熊本市が共同で作った検討会で、新たな法整備が必要だと指摘されています」