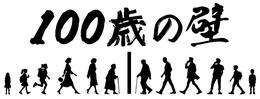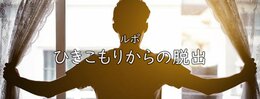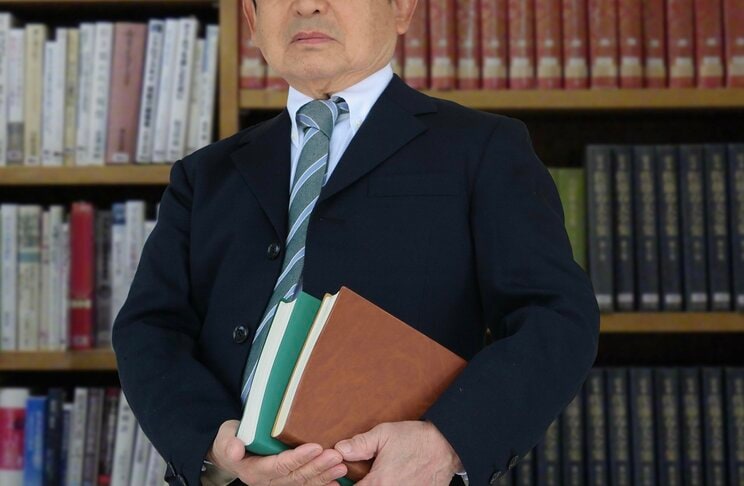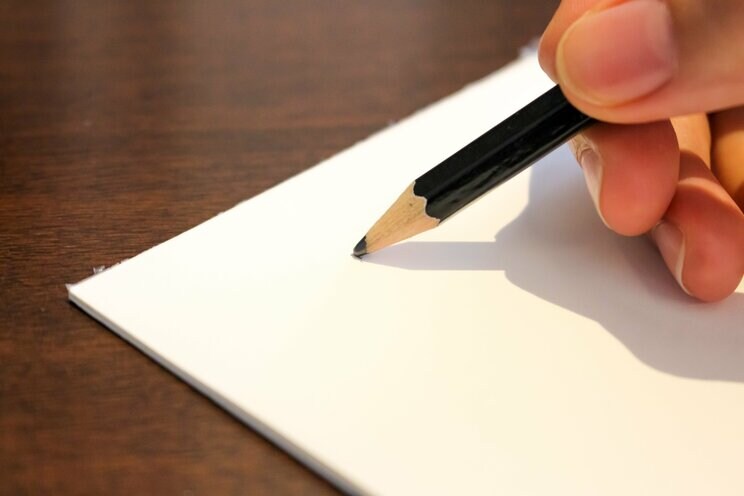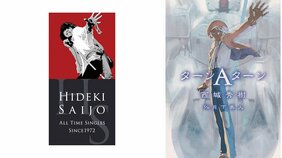「1万字以上を手書き」「研究会は若手の成果を吸い上げる場所」
ゼミ(研究室)という形で教授に師事する院生・研究者にとって、指導の放置は死活問題だ。だが、Aさんの周りには、逆に“とんでもない指導”を受けるアカハラも存在していたという。
「他の大学院には、高圧的な指導に悩む友人もいましたね。論文について重箱の隅を突くような指導を受け、イチからしっかり説明したら論文を投げつけられたとか。
ほかにも、『議論が雑』『センスが感じられない』といったコメントばかりで、具体的な改善点を一切示してもらえなかった友人もいました。そのくせ、他の教員には『アイツは研究に取り組んでいない』など、陰口を叩いていたそうです。
別の友人には、指導教授から『君はもっと書き方を学んだほうがいい』と言われ、『実際に手を動かしたほうが脳に定着する』と1万字以上を手書きで提出させられた人もいました。
友人も『さすがにここまでの無意味さは、理由をつけて嫌がらせしたいだけだと確信した』と憤っていました」(Aさん)
さらに驚くべきことに、アカデミックの世界では、指導するはずの教授が“研究実績を横取りする”という、泥棒のような行為まで横行しているという。関東のある大学で助教を務める30代男性・Bさんが語ってくれた。
「かつては、院生が書いた論文を指導教授の名義で公表したという例も聞きましたが、直接見たのは“共同執筆者”として指導教授の名前を追加させるやり口です。これはタダ乗り同然ですが、断ると指導放棄のほか論文投稿の推薦状も出ないため、応じざるをえません。
これは教員と学生に限らず、大御所と若手という研究者同士でも起こっています。業界の大御所が、相談に来た院生や若手研究者が独自に見つけた資料などを、無断で使用する例があるのです。大御所にとって、研究会は若手の成果を吸い上げる場所と化しています。
学会や研究会ではほかにも、若手の研究者が発表するときだけ、妙に質問したがるベテラン研究者がいます。しかも、そういう人に限って、高圧的な言葉遣いや激しい言葉で若手に質問し、ときには罵倒に近い言葉も遣っています」(Bさん)