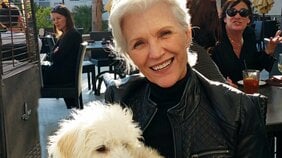円安、物価上昇で、生活環境の激変を国民が感じつつある
服部 2025年1月に『はじめての日本国債』という新書が刊行をされたのを機に、今回は国債市場でしばしば議論される論点について神田顧問にお聞かせいただければと考えています。思えば、私が学生のころから国債残高が増加し、経済学者などからそのことについての警鐘がなされながらも金利の低下傾向は続きました。それもあり、日本では財政再建の議論は盛り上がっていないように感じています。この点に関してどのようにお考えでしょうか。
神田 現在、世界中で財政は大きなテーマになっています。例えば最近でも、イギリスで放漫財政が招いたトラス・ショックのあと、14年ぶりの政権交代があったが、最大の論点の一つは財政でした。フランスでは62年ぶりの内閣不信任が通り、ドイツでは20年ぶりの解散総選挙となりましたが、ここでも財政規律がクリティカルな問題となりました。もっと言えば、アメリカでさえそうで、トランプ陣営はバイデン政権のIRA補助金をばら撒きとして批判して撤廃を約束し、ハリス陣営はトランプ減税を金持ち優遇と批判し、逆に法人税増税などを主張しました。
日本だけがその前提が違っていて、この理由について私も本当に内外のいろんな人に聞かれます。特に外国人からは、「日本人は次世代のことを考えないくらい利己主義か近視眼なのか、動物でも子供を大事にするじゃないか」、とまで聞かれて、「そんなことはない、日本人は先を考える賢明で、他人の幸福を考える正義感ある民族である」と反論しつつ、悲しかったことさえあります。たくさんあるのですが、四つだけ自分なりに整理してみます。
まず、借金を重ねて債務残高が増えても、長い間、金利が低下しており、利払い費が増えなかったという経験です。だから、1,000兆円を超える債務残高を意識できてないというのが一つ目です。
二つ目は、歴史的には財政に起因してインフレや通貨の暴落がしばしば起こるのですが、日本ではインフレや通貨安が起きない時代が長く続いてきたことから、その警鐘を鳴らしてもその深刻さが想像できなくなっていることがあります。他国と違い、ハイパーインフレ、通貨価値喪失の歴史的教訓が十分、受け継がれていないのです。
三つ目はやはり人口問題。生産年齢人口が何千万ずつ減ってしまうという未曽有の危機が実感を持って理解されておらず、その結果、借金で先送りした負担を、将来の世代に背負わせることの深刻さが認知されていない。
四つ目が、社会主義的、あるいは、パターナリスティックな政策を続け、持続不可能な企業もみんな守るようなことをしてしまった。永遠のフリーランチがあたかも可能であるような打ち出の小槌の幻想を信じるモラルハザードが浸透してしまいました。戦前の神風信仰のようなところがあります。その結果は悲惨で、20年以上、ずっと大規模な赤字を伴う積極財政を続ける反面、賃金も増えず、投資もなく、経済も成長できませんでした。例えば、円は実質実効為替レートで3分の1の購買力になってしまうなど、悲惨なことが起こってしまった。
そうはいっても、いよいよ長期金利が上昇傾向に転じ、円安、物価上昇で、生活環境の激変を国民が感じつつあるわけですよね。これは厳しい現実であり、そのため、過度の為替変動から国民生活を守るため、私も数十年ぶりの円買い為替介入に踏み切った次第です。
この変化は、ある意味で気づきの機会ではあるのですが、アジア通貨危機、あるいは、リーマン・ショックに加えて、東日本大震災や新型コロナなどを経験し、そのたびに多額の借金を積み重ねて、しかも、そのあとのノーマライズをそれほどしてこず、財政については、他国と異なり、日本は超拡大財政のままです。
これからさらに大きなショック、例を挙げれば、首都圏の直下型の地震とか、あるいは、東アジアで戦争みたいなことが発生したときに対応できるのか、財政的な余力が必要なのではないかという議論は大事です。安全保障を強化すべきと考えて防衛予算を拡充してきましたが、そうであれば、それが持続可能であるよう、安定財源を求めなければなりません。
また、高齢化によって社会保障の負担は増えていくのが当たり前であり、これも持続可能になるよう、制度の合理化と財源についてしっかり対応しなければなりません。特に、人口減少の中、借金のかたちで今の増大してく負担を先送りして、細っていく次の世代に押しつけることの影響を考えないと、倫理的にも問題じゃないかと思います。将来世代になりきって、今の時点でどのような意思決定を行うべきかというフューチャーデザインなどをしっかりやっていかなければならないと思っています。