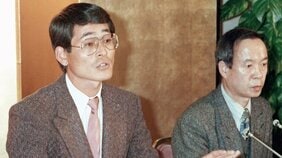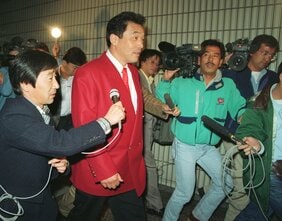「(新井は)広島弁でいうガンボたれですよ」
この新井のふるまいを見て、「9歳の頃から、まったく変わっていない」と感慨に浸っていた人物が広島にいた。かつて広島市の小学校教員で、現在は広島都市学園大学で子ども教育学部の学生たちを指導している佛圓弘修教授である。
ここで外務省も腰を引くアメリカに頑として筋を求める新井のルーツに迫ってみる。
佛圓は20代のときに自ら望んで教育困難校に赴任していった。その西区の小学校で他の児童よりも頭ふたつ抜け出た体の大きい少年を三年時に受け持つことになった。それが新井だった。
「広島弁でいうガンボたれですよ。負けず嫌いで勝負事は絶対に逃げないような子でした」
いつも強気で上級生にドッジボールで勝負を挑まれたら、真っ向から受けて立って勝利した。苦手な水泳では負けることが分かっていたが、それでも息が続く限り泳ぎ続けてクラスメイトからの喝采を浴びた。
一方で弱い者いじめは絶対に許さず、そんな現場を見つけると必ず抑止した。マサル君という障がいを持った子がクラスにいた。インクルーシブ教育などという言葉もなかった時代だが、人権教育の先進県と言われた広島では、当たり前のように一緒に授業を受けていた。
休み時間などで体の小さなマサルがからかわれそうな空気になると、新井は即座にそばに寄って、手を繋いでいた。「マサルをイジメる奴は、わしがシゴウしちゃるけえ、覚悟せえ」と無言でガードしたのである。
子どもたちに読者の習慣をつけてほしいと考えた佛圓は、自費を投じて学級文庫を作った。その中の一冊が「はだしのゲン」だった。9歳で親や兄弟を原爆で亡くしながら、戦後の混乱期をたくましく真っすぐに生きる少年ゲンの物語である。新井はそれをボロボロになるまで読み込んでいた。
「私は被ばく二世、新井君は被ばく三世です。私は『ゲン』のシリーズを揃えましたが、彼は授業が終わってもすぐに帰ろうとせずにいつも残って食い入るように読んでいました。心優しい少年が社会悪や矛盾に懸命に立ち向かう姿に心打たれたんでしょうね。ガンボたれは『僕はゲンになりたいんです』と、ことあるごとに言っていました」
その夢はまず小学3年生で実現する。「学習発表会」というクラスごとに出し物をする会があった。佛圓学級は、当然のように「はだしのゲン」の演劇を行なうことになった。そして児童の投票で決められた配役では、主人公の中岡元に新井が全員一致で選ばれた。
「あのイチローでも野球殿堂入りは満票ではなかったですよね。でもうちのクラスは、100%でしたよ(笑)」