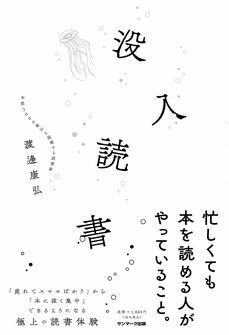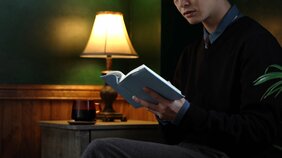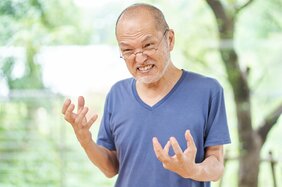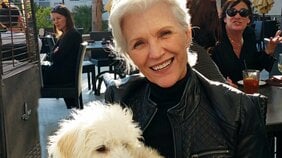人生が激変する「没入読書」…年間3000冊以読破の読書家が勧める、誰でも集中力と認知力が向上する読書法とは?
大ヒット中の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(著:三宅香帆、集英社新書)が描いているように、忙しさやスマホ依存などで、かつてのように本が読めなくなっている人は少なくない。単そんな人におすすめしたいのが「没入読書」という読書法だ。意志力や意識的な集中に頼らず、自然と本の世界に引き込まれていく状態に。どんな状態になり、どんなメリットがあるのだろうか。年間3000冊以上読破する読書家の渡邊康弘さんの著書『没入読書』より一部抜粋、再構成してお届けする。
認知力もある程度高められる
(3)頭がよくなる
本を読むことで、頭がよくなります。
ここでいう頭のよさとは「認知力」のこと。記憶力や思考力、計算力、言語力といった学力のことです。この認知力は、ただ文字を読むだけでも高まります。
読書のプロセスは、文字を目から画像として取得して、その画像を文字列に認識する。そして、文字列を意味に変換して、意味をイメージとして理解するものです。
このプロセスは、生まれてすぐに獲得しているという能力ではなく、生まれた後に段階的にトレーニングを積んで獲得するものです。
文字が速く読めるかは、このトレーニングの量、結局のところ経験則なわけです。量が多ければ多いほど優位になります。また、ますます重要性が高まる生成AIが作り出す情報も、多くがテキストのものです。そのため生成されたものを速く処理する力が大事になります。
さらに本は、自分と似たような考え、逆にまったく違う考えを学べます。いろいろな人の考えを知り共通項を探ったり、差異点を見つけたりすることは、頭のよさである認知力のアップにつながっていきます。
現在、行動遺伝学の世界では、遺伝要因が9割優位とされます。
しかし、本が好きになるかは、遺伝ではなくて環境要因にあるといいます。
たとえば、親に絵本を読んでもらって、本が好きになったという人も多いでしょう。また、親がよく本を読んでいるので、自分でもその行動を真似て本を読んでいたという経験をもつ人も多いはず。
実際、オーストラリアのある研究では、親が読書を楽しんでいると、子どもも20%増の割合で、読書を楽しんでいるといいます。
頭のよさである認知力も、訓練を行えばある程度高められます。
その訓練のひとつが、本を読むことです。
さらに、没入読書は通常の読書と比べ、本を読む量が圧倒的に増えます。そのため、認知力をアップさせるのにより適切といえるでしょう。
後編では没入読書によって得られる7つのメリットのうち残る4つのメリットを解説します。

2025/3/13
1,650円(税込)
208ページ
ISBN: 978-4763142047
忙しくても本を読める人がやっていること。
やる気に頼らず、自動的に集中できる本の読み方。
「本の内容が頭の中に入ってこない」
「働きはじめてから、読書に時間が取れなくなった」
近年、本を読みたくても読めなくなった人が多いといいます。
しかし、その理由は“忙しいから”だけではありません。
それは、スマホが身近になったから。
反射的に起こる通知に身を委ねてしまうと、
私たちはその刺激から抜け出せなくなるのです。
スマホの通知音などの刺激から脱し、本に集中できる方法、
それが「没入読書」です。
没入読書の特徴は3つ。
◉やる気や意志力を使わない
◉意識的に集中しようとしない
◉本を読むことに価値があると体に思い込ませる
没入であるフロー状態とは、「目標を設定」したり、
「呼吸を整えたり」するといった具体的な方法で導くことが可能です。
さらに、本の難易度が自分にとってやさしすぎても、
難しすぎても集中が切れてしまいます。
こういった具体的な方法で、
科学的に集中力を自動的に高める方法をお伝えします。
さらに、本書を読みながらすぐに実践できる
「47秒間読書」や「10分間指速読」から、
究極の没入読書である1冊20分で読める
「レゾナンスリーディング」も公開します。
没入する体験は、本を速く、たくさん読めて内容を忘れないことはもちろん、
ストレス軽減やアイデアが湧くといった副次的な効果もあります。
これで、忙しくても、スマホが手元にあっても
本に没入できるようになります。
【目次より】
◎まずは毎日の「47秒読書」で本と付き合いはじめる
◎スマホがあっても集中できる「10分間指速読」
◎読書前に「呼吸を整える」だけでも集中できる
◎【没入読書1】集中力の第一歩は「目標設定」にある
◎【没入読書2】「即時フィードバック」が集中状態を生み出す
◎【没入読書3】「チャレンジ」と「スキルのバランス」で集中が途切れない
◎めんどうだけど没入を生むのに効果的! 読書メモ
◎自己コントロール感を生み出す「読書ノート」
◎書店には「目的」をもって入店すれば失敗しない
◎生成AI時代だからわかった! 天才たちが大事にしていた「問い」