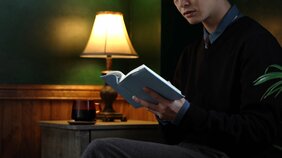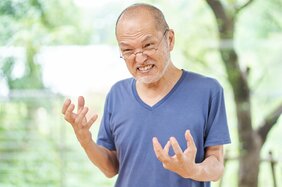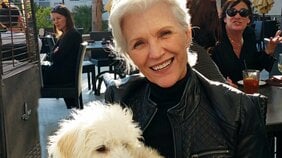本の世界に入り込む
本は、何百年という時間を超えて、その当時の情報を伝えてくれます。
本は、そこに描かれているところに身を置けば、その当時を疑似体験できます。
中でも小説では、まだ見ぬ世界に入っていくという感覚を味わえます。
村上春樹氏の本であれば、「井戸の底」という世界にどんどん入っていく感覚があります。井戸の底とは、村上氏の言葉を借りれば、好奇心そのもの。ドアがそこにあって、開くと別の世界へ足を踏み入れられるもの。
『ノルウェイの森』『ねじまき鳥クロニクル』『海辺のカフカ』『1Q84』『街とその不確かな壁』。私は、彼の小説を読んでいるとどんどんその世界に降りていく感じがあります。その暗い暗い世界の中で、気味の悪いキャラクターに出会います。それによって、自分という存在を再認識させられます。
阿部智里氏の『烏に単は似合わない』に始まる「八咫烏シリーズ」を読めば、平安時代のような世界を体感できます。
辻村深月氏の『かがみの孤城』は、自分自身の嫌な感情、あまり人に見せたくないような感情を癒してくれます。
歴史小説を読めば、その登場人物に自分を重ね、戦場を駆け抜け、外交や政治を疑似体験します。意思決定の仕方、人の見極め方、採用・育成の仕方……そのノウハウが歴史小説の中にあります。
経営者の多くが歴史小説を好み、特に戦国・安土桃山時代の織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、また『三国志演義』や『水滸伝』などの人気が高いです。経営者は、自分を登場人物に重ねて難局を疑似体験し、いま起こっている経営状況を判断しているのです。
本というのは文字情報だけですが、その情報を読むことによって起こる想像・連想を通じて、だんだんとその世界に入り込んでいけます。
その世界がイメージで現れてきます。このイメージはビジュアルイメージというケースもあるし、匂いや香りといったものだったりするかもしれません。何か音が聞こえてくるような感覚がするかもしれません。
これが、先ほどお話ししたゾーンやフローといわれているような感覚、研ぎ澄まされている感覚に通じているのです。