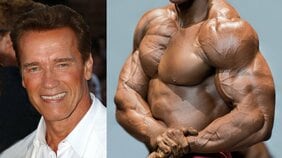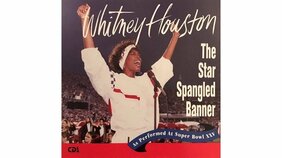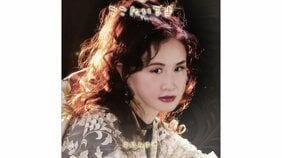息子の広治が80mの壁を超える
並外れた体格と体力で、中学時代には「怪物」と呼ばれていた重信氏。大相撲の時津風部屋からもスカウトされていたが、日大三島高校の陸上部で投擲競技と出会い、なかでもハンマー投げに手応えを感じる。最終的には4回転投げを極める重信氏であるが、高校では2回転投げから始めて、40mを少し超える記録を出していた。
投擲のための回転ができるようになると、小学1年生のときに喧嘩をさせられて、とっさに相手の腕を持ち、自分の身体を斜め後ろに預け、2回、3回と振り回して投げた感覚がよみがえった。ハンマーもそのようにして投げると、回転ごとに加速して、より遠くまで飛ぶのである。子どものころから私には、誰に教わるでもなく「良い投げの感覚」が身についていたようだ。その年の秋の試合で、私は46mまで記録を伸ばした。
そしてシーズンオフとなり冬の練習が始まり、3回転投げを試みた。そうしたらすぐに、1日に2mから3mずつ記録が伸びていく。家に帰って、そのことを父に伝えると、最初の日はまだ信じていたが、次の日に「また2m伸びた」と言うと、「そんなことがあるか」と取り合ってくれない。しかし日に日に記録は伸び、なんと1週間のうちに10m以上記録を伸ばして、57mまで達した。練習とはいえ、全国インターハイで優勝した選手の記録を上回ってしまったのだ。
(『野性のスポーツ哲学 「ネアンデルタール人」はこう考える』第1章の「進むべき道が定まる」より)
重信 息子の広治について言えば、10歳のときに初めて行なった空(から)ターン(ハンマーを持たずにターンする)の練習で、「よい投げの感覚」を完全につかみました。
3日間、基本動作の空ターンをやらせて、その後に投げさせた。子供用の軽いハンマーですけど、初めからレベルが全然違いました。そのころ撮った8ミリの動画があるのですが、今見てもすごいなと思います。
重心を膝に乗せて、回転軸を持って回っているんですよ。一般の学生はできないです。もちろん本格的に競技を始めるときには、他にもいろいろと覚えないといけないことがあるから、時間がかかります。ですからなおのこと、最初に基本的な動作は指導しておかなければいけないと思いましたね。
そして息子は競技を始めてから、必要な動きを自分で見つけていきました。今回の本の対談で息子が言っているように、「物事は自分で考えなければいけない」のです。競技者は精神面も技術的なものについても、貪欲でなくてはいけない。
ですが私の見るところ、どうもほとんどの競技者が指導者に任せてしまっている。だから、指導者を超えられないんですね。
話を戻しますと、「よい投げの感覚」というのは、ハンマーを投げるたびに起こるんです。悟りを開いたような感じで、「あ、これだ!」という感覚がある。そしてその「これが最高だ」という感覚は、毎回覆されるんです。一度として同じ投擲はありません。自分の現役時代もそうだったし、今、学生を指導していてもそうです。
また「できた」と思うときもあれば、「できない」と思う時もある。成功も失敗も積み重ねて最高のところまで行ったのは、息子の日本記録(84m86cm、世界歴代3位)は立派です。
私にも信じられない記録でしたが、その後の息子の試合を見ていると、「まだその上に行けたのではないか?」と思わせる投擲もありました。だから、「よい投げの感覚」というのは絶えず出てくるんです。
競技者たるもの、現状に甘んじることなく、よい投げが出たら、その上をまた目指すということを続けていかないといけません。