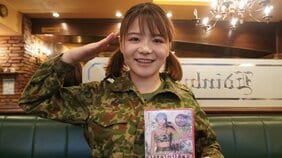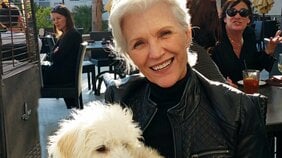時間外労働の制限で、モノが運べなくなる可能性も
2024年、多くのメディアで報じられ、社会全体の関心を集めた「物流の2024年問題」。SNSでも広く拡散され、日々の暮らしに直結する深刻な問題として、多くの人の耳に届いた。
簡単におさらいすると、「物流の2024年問題」とは2019年に成立した「働き方改革関連法」により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されることで生じる一連の課題を指す。
最大の課題として、輸送能力の不足が挙げられていた。政府が2023年8月に公開した「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」では、労働時間削減のために具体的な対応を行わなかった場合、2024年度には14.2%(営業用トラックの輸送トン数換算で約4.0億トン)、2030年度には34.1%(同約9.4億トン)の輸送力が不足するという試算も出されている(*1)。
特に、長距離輸送への影響は甚大だ。ドライバーの労働時間が制限されることで、これまで深夜や早朝の運行で成り立っていた輸送スケジュールの維持が難しくなり、途中で人員交代が必要となるケースが増加することが懸念される。これに伴い、人員確保の負担が増え、運賃の値上げや配送遅延などが発生する恐れもある。
ドライバーの労働時間短縮により、実際に運送回数の削減や配送エリアの縮小を余儀なくされた中小の運送事業者も多いという。公益社団法人宮城県トラック協会の調査によると、物流の2024年問題への対応準備として、「事業の縮小、輸送エリアの限定」を対策として挙げた企業もいたそうだ(*2)。
この問題は運送業者や荷主に限らず、一般消費者にとっても他人事ではない。現在のEC市場では「即日配送」や「翌日配送」が一般的なサービスとなっているが、物流負担の増大に伴い、今後はその維持が難しくなる可能性がある。
こうした状況を受け、国民生活センターは消費者に対し、「確実に受け取れる配達日時を指定し、その時間は必ず在宅する」「宅配ボックスや置き配、コンビニ受け取りを活用する」「複数の商品をまとめて注文・配達依頼をする」など、物流負荷を軽減するための行動を呼びかけている(*3)。