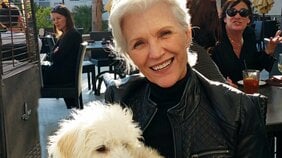「昼食は家庭で用意するのが常識」
別の30代の女性教員は、「何でも保護者の要求を飲むことが『寄り添う』ことではない」と話す。
「保護者に送迎をお願いしているのは、登下校の時間外に子どもが1人で外を歩いていて、事件や事故に巻き込まれないかを心配してのこと。
『寄り添う』というのは、何でも保護者の要求をのむことではなく、目標や目的があって、そこに至るまでに必要な支援をすることだと思います」
その上で、こうした保護者への「対応策」について具体的に話してくれた。
「私だったら、迎えに来て欲しい旨を保護者に伝え、『管理職に確認する』と言って一回電話を切ります。また同じ方から電話があったら、管理職と話してもらいます。
働きながらの子育ては大変でしょうし、それは否定せずに一部理解していることは伝えたほうがいいと思います。
電話対応では、話している間にヒートアップする方もいますし、ただ愚痴を言いたいだけの方もいます。
保護者がどんなタイプかを見極めて、早めに電話を切るのか、ある程度話を聞いて鎮火させてから切るのか決めています」
一方、「欠席者が増えると仕事量が減って楽になる」という声もある。別の20代の女性教員は次のように話す。
「中学受験期にかかわらず、普段から旅行などを理由に平気で学校を休ませる保護者も増えました。昔のように『学校は絶対行かなければいけないもの』と考える保護者は年々減っていると感じますよ。
受験の時期になると、受験しない子どもたちは『学校に来る友達が少なくなって寂しい』と言いますが、教師は仕事量的に楽になりますね」
こう話した上で、同女性教員は「でも昼食は家庭で用意するのが常識だ」と続けた。
「親には欠席の理由と、いつまで休むかを連絡してもらう決まりになっています。でも、それ以外のことをいちいち学校に連絡してくる親や、この投稿のように給食だけ食べに行かせようとするモンスターペアレントは私の学校では聞いたことがありません。休ませるのであれば、昼食は家庭で用意するのが常識だと思います」