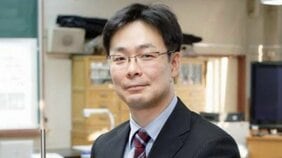「学力向上」という大義をまとった教育への政治介入
「どんな複雑な問題にも決まって短く、単純で、間違った答えがある」と言ったのは、アメリカの著名なジャーナリスト、H・L・メンケンだった。
1980年代以降、市場原理を導入して学校や教員を競い合わせれば公教育も改革できるという、あまりにも安易な新自由主義教育「改革」が、世界規模で子どもたちの教育をダメにしてきた。
日本も例外ではない。大きな転機となったのが、2007年に43年ぶりに復活した全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)だった。実は以前にも全国学力テストは行われていたが、地域・学校間の過度な競争を招いたことなどを理由に、1964年に中止された歴史的経緯がある。
それが、2004年のいわゆる「PISAショック*1」で高まった「ゆとり教育」への反動を機に、名前を変えて復活したのだ。
しかし、「全国学力・学習状況調査」を純粋な学力調査と見るのはナイーブで、むしろ政治が教育に介入するためのツールと見る方が正しいのではないだろうか。それも「学力向上」という大義をまとったツールだ。
もし、その名の通り、生徒たちの日頃の学力を調査することが目的ならば、地域ごとに一部の生徒を抽出して調べれば十分だ。しかし、2007年当時の第一次安倍政権は、77.2億円*2もかけて悉皆式(しっさいしき ※一斉)での実施にこだわった。
その後、民主党政権で一度は抽出式になったものの、第二次安倍政権はわざわざ悉皆式に戻すという執拗さを見せた。なぜか。その理由は、2014年に明らかになる。
2014年、第二次安倍政権は、全国学力テストの結果を、従来の自治体別だけでなく学校別に開示できるよう規制緩和した。全国の小学校6年生と中学校3年生が共通のテストを受け、自治体の教育委員会が容認すれば学校別の成績も開示される……。
当然、知ることができるなら自分の子どもの学校の成績を知りたい、少しでも成績の良い学校を選択できるようにして欲しい、と求める保護者も出てくる。
また、教育の政治的中立性の原則から、教育問題にはなかなか手を出せずにいた政治家らも、77.2億円もの税金に対する「費用対効果」という観点から、当然のように教育現場に「結果責任」を求めることが可能になった。
こうして、日本全国の地方自治体が全国学力テストの点数競争に翻弄されるようになっていったのだ。