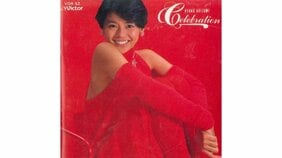非正規教員への依存こそが、教育現場から持続可能性を奪った
では、教員不足の原因はどこにあるのか? 慶應義塾大学の佐久間亜紀は、2000年代の小泉政権下で始まった地方分権改革と規制緩和による正規雇用教員の削減と非正規教員への依存こそが最大の原因だと指摘する。
2001年の義務標準法の改定は、それまでは生徒40人に対して1人の正規雇用教員の配置が義務づけられていたが、それを複数の非正規雇用教員で分割可能にした。
2004年の義務教育費国庫負担制度への総額裁量制の導入は、教職員給与費の総額範囲内であれば教員の数・給与・待遇を自治体が決められるように規制を緩和した。
2006年には、公立学校教員の給料の国庫負担が2分の1から3分の1に削減されたため、多くの自治体が非正規教員を雇用することで教員の数を揃えることを優先した。こうして、正規教員の数と給料が減る反面、非正規教員が激増していったのだ*5。
非正規教員は教員採用試験に受からなくても教壇に立てる反面、給料も安く、それだけで生計を立てることは難しい。教壇を去る心理的ハードルも低く、離職率も高いため、出入りの激しい「回転ドア」の図式がそこに生まれる。
つまり、非正規教員への依存こそが、教育現場から持続可能性を奪ったのだ。
「教員不足」という問題は、新自由主義的な政府による度重なる規制緩和によって作り出されたものだ。それを今、さらなる規制緩和で解決しようとする姿には、悪意すら感じられる。
政府は、2007年の教育職員免許法の改定で免許取得条件を厳格化し、さらには教員免許更新制度まで導入。このように、正規のルートで教員を目指す者への締めつけによって教員不足を加速させつつ、他方で「副業先生」をどんどん現場に送り込もうとする政府のダブルスタンダードを、私たちはどのように理解したらよいのだろうか。
大事なのは、終身雇用資格の剥奪や正規公務員から非正規契約雇用への切り替えといった、教員の身分保障の脆弱化はもはや世界的な傾向となっているということだ*6。
「副業先生」を増やすことで教職のさらなる非正規化と時間労働者化は避けられない。教員免許は、持っていれば「良い教員」というわけではないが、教員として子どもたちの前に立つための最低限の保証だ。「特別免許状」の交付に、そして教員の非正規化に、いったいどこで歯止めをかけるのだろうか。