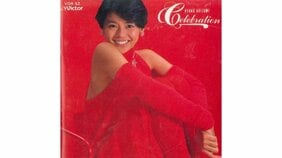「何で教員になったの?」
1980年代、瀕死だったアメリカの大手自動車会社クライスラーを立て直した伝説の経営者、リー・アイアコッカがこんな言葉を残している。
「真に理性的な社会では、最も優秀な人間が教員になって、他の人間はその他の職業で我慢するしかない」
残念ながら、私たちが生きるこの日本は、アイアコッカが切望した「真に理性的な社会」からは程遠い。
高校から大学院まで計8年のアメリカ留学を経て、帰国後に通信教育で2年半かけてやっと免許を取得して教員になった私に、人々は繰り返し同じ質問をした。
「何で教員になったの?」
もっと良い仕事に就けただろうに……。一様に驚く人々の反応は、日本という国が、教員が尊敬されない社会であることを物語っていた。
それと比べ、フィンランドでは教員の社会的地位が高い。そもそも大学院を出ていないと教員になれず、教員採用試験も狭き門だ。給料も待遇も良く、フィンランドの高校生の間で人気ナンバーワンの職業が教員だという。
そんな環境で学ぶことのできる生徒は、きっとスポンジのように教員から知識を吸収するだろう。
「教員の社会的地位の向上なしに日本の教育改革はあり得ない」。私が6年半の教員生活にピリオドを打ち、研究者の道を目指したのはそんな理由だった。
政府は特別免許状の「積極活用」によって、いわゆる「副業先生」をどんどん現場に送り込むことで教員不足を解消しようとしている。
私は、特別免許状が必ずしも悪いとは思っていないし、逆に正規の教員免許を持っている人間が必ずしも良い教員だとも思っていない。私自身、教員になったのは28歳の時だった。それまでに得たさまざまな経験は教員として確実に役に立ったし、人々が第二の人生として教員を目指し、多様な人々に子どもたちの教育に携わってもらうのは好ましいことだと思っている。
ただ、特別免許状の乱発による教員不足の解消が、問題の本質的な解決につながらないことは書いた通りだ。