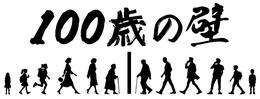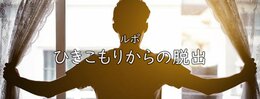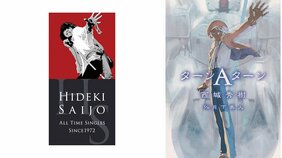“カカオショック”直撃の影響で…
チョコレートの差し出しを強要したり、もしくはホワイトデーのお返しを強要するなど、バレンタインデーのイベントにちなんだトラブルを指す「チョコレートハラスメント(チョコハラ)」。
その定義や具体的な事例について、ハラスメントなど職場でのトラブルに詳しい「エンカウンター社会保険労務士法人」の社労士に話を聞いた。
「広義の意味で、『性別や年次あるいは階層など、特定の社員が負担を強いられる社内イベント』はハラスメントに繋がる懸念があります。
バレンタインデーにちなんだ『チョコハラ』の事例では、会社の風習として『男性社員にチョコレートを贈る』という文化が仮にあったとします。その際、イベントを張り切りたいタイプの声の大きい女性社員が『新人も含めてみんなでお金をカンパしよう』と言い、当事者の賛同を問わず、断りづらい環境を生み出す。それ自体がハラスメントになる可能性があります。
さらに資金をカンパして新人や後輩に『チョコレート買いに行ってきて』と労働時間外に業務を強要したり、チョコを渡された方もお返しを倍にしないと会社での立場が危うくなるような状況も『チョコハラ』になります」(社労士、以下同)
今年はバレンタインデーを前に、チョコレートの主原料であるカカオ豆が高騰する「カカオショック」の影響で、スーパーマーケットの店頭にある高カカオ商品が前年比2割減の推移となっているほか、「パナソニック」が実施した「2025年バレンタイン最新意識調査」では、調査対象者である10~60代の女性800人のうち、「物価高で生活にお金がかかるから」などの理由から、3人に1人がバレンタインの予算を見直すと回答している。
カカオショックの直撃もあり、もはや縮小傾向にあるバレンタインイベント…。実際に地元紙に勤務していたAさんの事例を話してみると、
「Aさんの場合、『これに従わなかったらどういった不利益があるのか』を容易に想像できない状況だと思います。その際、チョコを渡さざるを得ない。当事者が心理的にも経済的な面からも不快感や負担を感じているなら、それはハラスメントに値します」