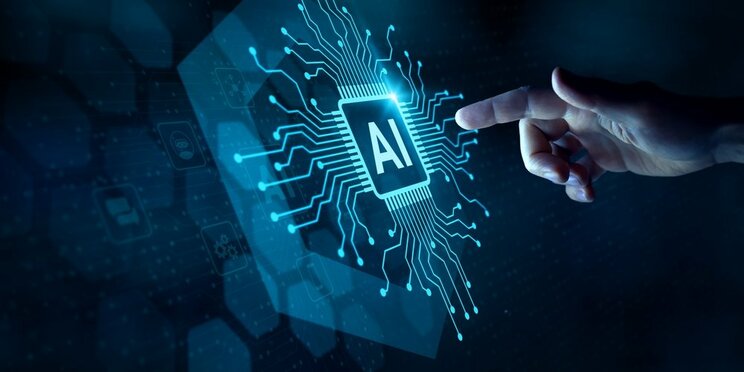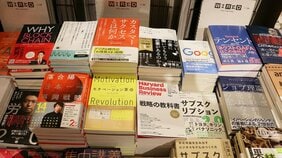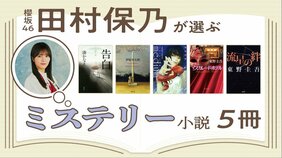本を読む余裕のない社会って、おかしくないですか?
こんな経験をネットに綴ったところ、大きな反響がありました。私のもとに、さまざまな「私も働いているうちに本が読めなくなりました」という声が集まったのです。
本書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、2023年1〜11月にウェブサイト集英社新書プラスで連載した内容に加筆修正したものです。ウェブ連載をしているとき、一番私のもとに集まった感想は、「自分もそうだった」という声でした。
「私も働き始めて、本が読めなくなりました」「私の場合は音楽ですが、働き始めるとなかなかバンドを追いかけられなくなりました」「本を読もうとしても、疲れて寝てしまって、資格の勉強ができないんです」
そんな声がたくさん、たくさん寄せられました。
「ああ、働いていると本が読めなくなるのは、私だけじゃなかったんだな」そう感じました。そもそも日本の働き方は、本なんてじっくり読めなくなるのが普通らしいのです。そういう働き方がマジョリティなのです。たしかに週5日はほぼ出社して、残りの時間で生活や人間関係を築いていたら、本を読む時間なんてなくなるのが当然でしょう。
しかし──私は思うのです。
「いや、そもそも本も読めない働き方が普通とされている社会って、おかしくない!?」
AI時代の、人間らしい働き方
最初に伝えたいのが、私にとっての「本を読むこと」は、あなたにとっての「仕事と両立させたい、仕事以外の時間」である、ということです。
つまり私にとっての「本も読めない社会」。それはあなたにとっては、たとえば「家族とゆっくり過ごす時間のない社会」であり、「好きなバンドの新曲を追いかける気力もない社会」であり、「学生時代から続けていた趣味を諦めざるをえない社会」である、ということ。
私にとっては、読書が人生に不可欠な「文化」です。あなたにとってはまた別のものがそれにあたるでしょう。人生に必要不可欠な「文化」は人それぞれ異なります。
あなたにとって、労働と両立させたい文化は、何ですか?
たとえば「海外の言語を勉強すること」「大好きな俳優の舞台を観に行くこと」「家族と一緒にゆっくり時間を過ごすこと」「行きたい場所へ旅行に行くこと」「家をきちんと整えて日々を過ごすこと」「やりたかった創作に挑戦すること」「毎日自炊したごはんを食べること」……など、自分の人生にとって大切な、文化的な時間というものが、人それぞれあるでしょう。そしてそれらは、決して労働の疲労によって奪われていいものではない。
もっと簡単に言うと、「生活できるお金は稼ぎたいし、文化的な生活を送りたい」のは、当然のことです。しかし、週5フルタイムで出社していると、それを叶えることは、想像以上に難しい。私はそれを社会人1年目で痛感しました。
私だけではないはずです。今を生きる多くの人が、労働と文化の両立に困難を抱えています。働きながら、文化的な生活を送る──そのことが、今、とっても難しくなっています。
ChatGPTが話題になり、AIが私たちの仕事を奪う、と言われている世の中で、私たち人間が生きる意味とは何でしょうか。仕事をただ長時間こなすだけのマシーンではなく、文化的な生活をしてこそ、人間らしい生き方をしていると言えるのではないでしょうか。しかし労働によって文化的な生活をする余裕がなくなっているのだとすれば……それこそ、そんな働き方はAIに任せておけ、と言いたくなります。
自分の興味関心や、生活によって生まれる文化があってこそ、人間らしい仕事が可能になる。
AI時代における、人間らしい働き方。
それは、「労働」と「文化」を両立させる働き方ではないでしょうか。