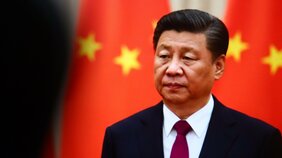国民の手取りを静かに、しかし確実に削っていく高市早苗
「増税はしない」
高市政権は、そう繰り返し説明している。確かに、消費税率が引き上げられるわけではない。新たな増税法案が国会を通る予定もない。だが、その言葉を額面通りに受け取って安心しているとしたら、かなり危うい。
なぜなら、政府が言う「増税」と、国民が実際に感じる「負担増」は、もはや同じ意味ではなくなっているからだ。
税率が据え置かれていても、手取りが減れば生活は苦しくなる。家計にとって重要なのは、言葉の定義ではなく、最終的に自由に使えるお金がいくら残るかである。
2026年4月は、「増税が始まらない年」ではない。増税という言葉を使わない大規模な国民負担増が、一斉に動き出す年だ。
しかもそれは、分かりやすい形ではやって来ない。制度は複雑に分解され、名目もバラバラだ。だからこそ、多くの人が気づいたときには、すでに生活が圧迫されている。
高市政権が選んだのは、税率を引き上げる正面突破型の増税ではない。社会保険料、支援金、負担金、そして物価上昇による実質負担――そうした「税ではない」形を組み合わせ、国民の手取りを静かに、しかし確実に削っていく方法だ。いわばサイレント増税である。
その象徴が、26年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」だ。少子化対策の財源を確保するため、すべての医療保険加入者から広く徴収される仕組みで、独身者も、子育てを終えた世代も対象になる。
政府は「月数百円程度の負担」と説明するが、年額2400円から最大で2万円程度となる決して小さい負担ではない。そもそも、問題は金額の大小ではない。税ではない名目で、事実上の強制負担が恒常化するという前例が、ここで作られてしまうことだ
インフレが続くだけで自動的に負担が増える仕組み
これに加えて、社会保険料の上昇圧力は今後も続く。高齢化を理由に、医療・介護・年金の保険料は長年にわたって引き上げられてきた。
会社員であれば労使折半のため負担感は見えにくいが、給料から差し引かれる金額は確実に増えている。保険料は税と違い、「増税だ」と大きく報じられにくい。しかし、可処分所得を削る効果は同じである。
さらに見逃せないのが、物価上昇による実質的な税負担増だ。名目上、税率や控除額が変わっていなくても、物価が上がり、賃金がわずかに上昇することで、課税所得が増えたり、より高い税率区分に押し上げられたりする現象が起きる。
いわゆるブラケットクリープである。これは制度上の「増税」ではない。だが、実質的な生活水準が改善していないにもかかわらず、税や社会保険料の負担だけが重くなる。
政府が特別な決定をしなくても、インフレが続くだけで自動的に負担が増える仕組みが、すでに出来上がっているのだ。
そして、インフレそのものがもたらす負担、いわゆるインフレ税も見逃せない。物価上昇によって現金や預金の実質価値が下がる一方、政府が抱える巨額の債務は実質的に軽くなる。誰にも請求書を出さないまま、国民全体から静かに負担を吸い上げる仕組みである。