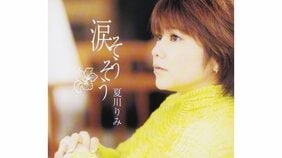日本史を教えろ、というタカ派からの圧力で「歴史総合」という科目が新設された
前川 「日本史を教えろ」というタカ派政治家の圧力があったこともあって、世界史必修はやめて、新たに世界史の中で日本史を学ぶという科目「歴史総合」が作られました。2022年度から高校で2単位の必修科目として。18世紀以降の世界史と日本史を一緒に学ぶという科目で、18世紀はさらっとやって19世紀以降はしっかりやる、と。日本の場合には、いろんな外国の船が日本にやってくるようになって、いよいよ日本が開国して、という辺りからしっかり勉強しましょう、ということで、これはいい指導要領の変更だったと思います。
それまで必修だった世界史は、メソポタミア文明や黄河文明から勉強するわけで、古代文明も大事だけれど、そこから勉強していたら高校3年全部使っても足りない。現代を生きる上で必要となる歴史の常識を身につける意味では、18世紀以降の日本史と世界史を両方学ぶ「歴史総合」という科目を作ったこと自体はよかった。
ただ、もともと世界史を教えていたとか日本史を教えていた先生が、両方教えるのは難しいということがありますが、それは先生にも勉強してもらうしかない。勉強し、世界史の中に日本史を位置づけて学んでもらう。学ばないことは教えられませんから。
私は自主夜間中学の運営に少し関わっています。「あつぎえんぴつの会」(神奈川県)と「福島駅前自主夜間中学」(福島県)です。大人のフリースクールみたいなもので、自由に何を勉強してもいいので、あつぎえんぴつの会では、神奈川県の中学の社会科の先生だった津田憲一さんという方を招いて沖縄戦の話を聞いたことがあります。
津田さんは言わば市井の人で、学者じゃない。でも中学の社会科教師だから、近現代史も仕事として教えていました。今はもうリタイアしていて、元社会科教師。彼は「沖縄戦の実際を自分の目と耳で確かめよう」と、何度も沖縄に行って、沖縄戦を生き延びた人たちの話も直接聞いたりして、一生懸命自分でファクトを集めて、それを元にして中学で教えていたんです。この人の話を、自主夜間中学に来てもらって聞きました。
林 そうなんですね。津田憲一さんは、私の『沖縄戦』の参考文献リスト(342ページの4番目)で紹介している『加計呂麻島旅日記』を書かれた人で、最初は沖縄に行かれていたようですが、その後、主に加計呂麻島(かけろまじま、鹿児島県大島郡の奄美群島の島)に通って聞き取りを重ねた方ですね。
前川 はい、その方です。津田さんは沖縄や奄美で「集団自決」についての聞き取りを続けてきた。座間味島では、村の助役だった宮里盛秀さんが父の盛永さんに「軍からの命令で自決しなさいと言われている。一緒に死にましょう」と話したということを、その場にいた盛秀さんの2人の妹さんから聞き取ったそうです。津田さんが最近出されたのが『奄美“幻”の「集団自決」』(南方新社、2025年)という本で、林さんが参考にされた『加計呂麻島旅日記』も収録されています。
津田さんは、自分の活動を説明して「自分は語り部ではないけれど、語り部の伝え部です」と言っています。語り部から聞いたものを伝える、と。本来は歴史学そのものが、語り部の伝え部だと私は思います。
この津田さんのように、自らの問題意識を持って自分で勉強し、勉強するだけじゃなくて自ら足を運んで、事実を収集するところからやろうとする。そこまでできる人は少ないでしょうが、少なくとも中学や高校の社会科の教師として歴史を教える立場にいる人は、教えるだけじゃなくて学ぶということが非常に大事だと思います。
だから教師にとって、「忙しいから学ぶ暇がない、時間がない」というのは、教師の勤務条件として、非常に問題がある。教師が自ら学ぶ時間をしっかりと取れるように条件整備をすることは行政の責任ですが、逆に「こういう様式で報告を出せ」とか、役所仕事みたいに文書を作って上に上げるような仕事が学校現場でもすごく増えている。
これはよくない。そういうものをできるだけなくし、先生たちがもっと自由に、たとえば夏休みに自ら自主研修で沖縄に行っていろんな勉強をしてくる、ということができる時間を与えてあげることが非常に大事です。
でも実際の教育政策は逆を行っている。「学習指導要領を勉強しろ」とか、国側が望むような教師を作ろうとする方向に戻りつつある。
国策で教師を養成する師範学校は戦後廃止になったが……
前川 戦後の民主教育を始めるときに、師範学校を全部廃止したんです。師範学校というのは国策で教師を作る学校だったわけですが、戦後は「教師を作ることだけを目的にする学校はいらない。大学で教師を育てる」という考え方に転換したのです。大学には学問の自由がある。国策で教師を作るのではなく、大学での自由な学びを土台にして教師を養成するという考え方になったんです。
しかし今また国が政策として、教員養成の大学の教育内容にすごく口を出すようになってきてる。コア・カリキュラムといって「こういう内容を必ず教員養成の際に盛り込め」と細かく指示するようになり「国策で教師を養成する」という師範学校型に戻りつつある。これは非常に危ない。
大学は本来自由な学びの場であり、学問の自由は憲法23条で保障されているわけですが、学問の自由は大学の先生にだけ保障されているわけじゃなくて、基本的人権ですから人間であれば誰でも学問の自由を持っているはずで、当然小・中・高校の先生も学問の自由を持ってなきゃおかしい。私は教師という仕事は、大学であれ小・中・高校であれ、自ら学ぶということと不可分だと思います。自ら学ぶ時間がないという今の教師の勤務実態は、何とかしなきゃいけない。そのゆとりは回復しなきゃいけないと思います。
ただ、学習指導要領だとか、教科書検定だとか、教員研修という形で、上から「こういうことをこう教えろ」という圧力が、この30年間ずっと強まり続けている。それは自民党の政治が上にあったことが原因です。私はその下で仕事をしていましたから、そういう経験を何度もしました。