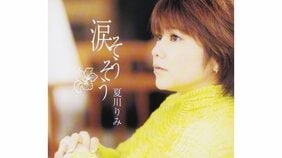道徳が「教科」にされたことは「戦争ができる国民作り」につながる
前川 「新しい歴史教科書をつくる会」ができたのも、「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」ができたのも97年ですから、大体この30年の教育の流れが大きく右傾化していく出発点がこの年だと思います。教育の右傾化はどんどんひどくなっている。2006年には教育基本法が改正され2018年には道徳が教科化されました。
この道徳の教科化というのは、「国が作った国民道徳を学校教育で教える」ということです。道徳教育を国が進めるのは、本当に危ない。「道徳の時間」というのは、私が小学生の頃からありました。これは1958年に岸信介内閣のときに設けられた。でもその頃の日教組(日本教職員組合)の組織率は86パーセントでしたから、現場サイドで握り潰したケースが多く、国が期待したような効果は上げなかった。
それに対して、「こういう曖昧な位置づけだからよくない、国語や算数のようにちゃんと教科にすべきだ」という政治の動きが強まった。教科にするということは、国が検定する教科書を使わせるということと、「学習成果を評価する」ということを意味します。
岸信介内閣のときに導入した「道徳の時間」には教科書はなかったし、学習成果を評価することもなかった。それに対して「だからダメなんだ。ちゃんと国家の道徳を国民に教えるためには、戦前の修身のように教科にしなければいけない」と言う人たちが90年代後半から一気に力をつけてきた。
特に2000年に森喜朗さんが総理大臣になったのが大きなきっかけでした。小渕恵三総理が突然倒れたので、棚ボタ式に森さんが総理になって、森内閣のもとで教育改革国民会議が、初めて公文書で「教育基本法の改正」と「道徳の教科化」を打ち出したんです。これが決定的に日本の教育の右傾化の流れを作りました。
そして2006年の教育基本法の改正。この改正で盛り込まれた言葉が「道徳心」「国を愛する態度」などという言葉です。その言葉を入れさせた人たちが考えている道徳心というのは「国家が作る国民の道徳」ですから、教育勅語のようなものを考えている。
でも私は本来、道徳というのは、憲法で保障された思想、良心の自由の中にあるのであって、1人1人道徳は違うはずだと思います。1人1人違う道徳だけれども、その最大公約数的なものが法律になっていて、「人を殺したら罰せられる」とか「物を盗んだら罰せられる」とか、刑法の中に最大公約数的なものはあるけれど、それ以上のもの、罰せられない悪事というのがどこまであるか、あるいは、法では実現できない正義とか善とかとは何なんだろうかというのは、1人1人の精神の自由の中にしかないと思うのです。
しかし「日本人には日本人の道徳がある」という考え方をいまだに持っている人たちがいる。というか、むしろこの30年間に拡大再生産されている。それで第二次安倍政権で、ついに道徳の教科化まで実現してしまった。第一次安倍政権でもやろうとしたけれど、第一次安倍政権は1年しかなかったので、教育基本法の改正まではやったけれども、道徳の教科化まではできなかった。それが2018年についに小学校で道徳の教科化が始まり、翌年は中学校で始まった。これは本当に危ないと思います。
道徳の教科書は、検定のしようがないと思うのです。他の教科であれば、それぞれバックグラウンドとしての学問があり、歴史の教科書であれば歴史学があるので、学問の成果に基づいて検定すればいいわけですが、道徳の検定の基準になるものって、ないはずなんです。
でも学習指導要領はあるんです。1958年に岸信介内閣のときに作った学習指導要領が、その後多少の変遷を経て残っています。たとえば「日本人としての自覚をもつ」と学習指導要領に書いてあります。「父母、祖父母を敬愛する」という徳目も書いてある。でも世の中には敬愛できない父母も祖父母もいるはずです。
暴力をふるったり、育児放棄したり、毒親と言われる人たちもいるわけで……。それなのに「父母、祖父母だから必ず敬愛しろ」なんていうことが学習指導要領の道徳編には書いてある。
そして今、教科になった道徳の教科書には、全部「正解」が書かれている。「全体のために自らを犠牲にする」「全体に奉仕する」「貢献する」ということが美徳とされて、「自分を活かす」なんていうことを美徳に書いてある教材はほとんどない。むしろ「我慢しろ」とか「わがまま言うな」とか「自らの成功を求めるな」とか「自己抑制や自己犠牲こそが美徳だ」と。これは従順な兵士を育てるにはもってこいでしょう。
だから道徳の教科化は「戦争ができる国民作り」につながる。昔の日本軍の兵隊のように「命令されたら何でもしてしまう」権力や権威に非常に従順な兵士を作る。だからこの道徳の教科化は本当に危ないのです。