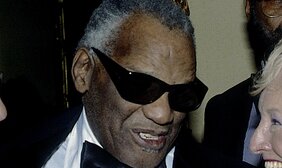「物乞いのよう」と揶揄される
最初の大きな旅行から戻ってきたモーツァルトは、数か月をザルツブルクで過ごした後で、今度はウィーンとイタリアに向けて旅立ちます。ウィーンやイタリアも音楽において非常に重要な地でした。
イタリアを訪れたモーツァルトは、ヘンデルの時代に大活躍したカストラートのファリネッリに出会い、その後ローマへ向かいます。
ここローマでもその天才ぶりを示すエピソードがありますので、紹介しておきましょう。
ミケランジェロの描いた「最後の審判」で有名なヴァチカンのシスティナ礼拝堂には、「ミゼレレ」という門外不出の曲がありました。
「門外不出」というのは、おそらく楽譜を決して外部に見せないということだと思われます。演奏を聴くことはできたようですが、モーツァルトはその曲をたった一度聴いただけで記憶し、楽譜に書き写してしまったというのです。その後モーツァルトは、ヴァチカンにおいて教皇への謁見が許されています。
そのようにしてモーツァルトは、ザルツブルクに戻っては、また旅に出るという生活を続け、青年へと成長していきます。
大人に近づくにつれて親子が意識していたのは、宮廷の作曲家として定職に就くことでした。しかし、青年に達したモーツァルトは、その才能に疑いはないものの、「神童」と呼ばれるには大きくなりすぎていました。
モーツァルト親子に対する周囲の見方も、この頃から徐々に変わっていきます。
親子はミラノを訪れた際、フェルディナント大公に雇用を願い出ています。この時、モーツァルト15歳です。フェルディナントは、ウィーンで女帝として知られているマリア・テレジアの息子でした。マリア・テレジアは息子に宛てた手紙の中で、こう忠告しています。
「世間を物乞いのように渡り歩く」モーツァルト家の習慣は、大公の奉公人たちに悪影響を及ぼすことになるだろう、と。
その後も、モーツァルトは宮廷で雇われることを望んでいましたが、一度も望む仕事を得ることができませんでした。ここは天才モーツァルトのイメージとは大きく離れているところかもしれません。
その理由は、演奏と引き換えに報酬を期待するモーツァルト親子の姿が、「物乞い」のように映ってしまったこともあるのでしょう。「神童」の頃ならば可愛げがあった姿も、青年になるにつれ徐々に疎まれてきたのです。
モーツァルトが16歳になる頃、故郷ザルツブルクでは、彼にとって大きな出来事が起こります。それまでの大司教だったシュラッテンバッハ伯が亡くなり、その後継としてコロレド伯が就任したのです。
シュラッテンバッハ伯は、父レオポルトの雇い主でしたが、モーツァルト親子の活動に対しては非常に寛容でした。しかし新たに大司教に就任したコロレド伯はそうではありません。休暇に対しても寛大ではなく、その結果、音楽活動が制限されてしまいます。
そうした不満の中、モーツァルト一家はある行動に出ます。母親と共にパリへ向かい、就職活動を始めるのです。
この時点でモーツァルトは20歳を過ぎていましたが、いまだに宮廷作曲家、宮廷楽長という望む職に就けずにいました。けれど、それもうまくいきません。
パリで、彼らの面倒を見ていたグリム男爵は、父レオポルトへの手紙で、「モーツァルトがパリでやっていくためには、才能は今の半分で十分だが、2倍の如才なさが必要だ」と書いています。
この頃からモーツァルトには、人にうまく取り入る才能や、金銭管理の才など、音楽以外の能力の欠如があらわになっていきます。