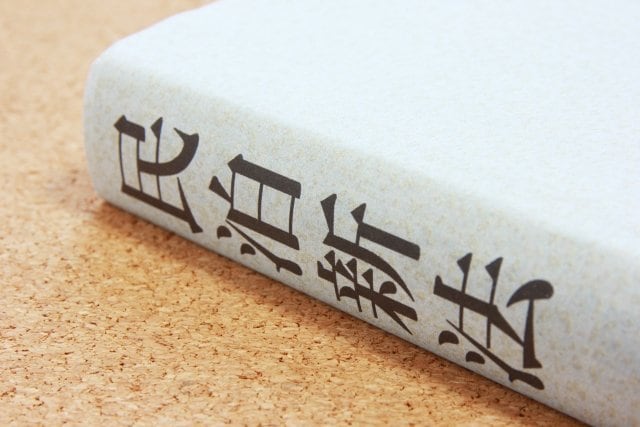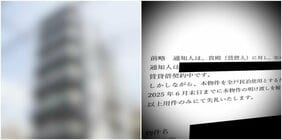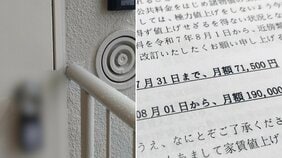軽井沢は民泊に厳しいはずなのだが…
営業するには「旅館業法の簡易宿所営業許可」が必要だが、これも別荘地や住環境を守る目的から、町は積極的に認めていない。正直言って合法的に民泊を行うのは非常に困難、いや不可能な地域といえる。
それなのに生鮮品を買い漁る中国人旅行者が異常なほどいるということはどう考えても不自然で、隠れ民泊をしているのだろうか(真実はわからないが)。
あくまでも一般論として、よくある隠れ民泊、隠れハイヤー(タクシー)のスキームは 「知人宅」「友人への短期貸し」「身内利用」や「友人の送迎」「知人の送迎」を装うケースだ。
利用者は中国本国でSNSやWeChat経由で予約をし、 中国国内でAlipayやWeChat Payなどで事前決済をして日本側には痕跡を残さないというカラクリのようだ。
物件の様子も住民票なしで電気・水道がほぼ使われないばかりか、 住民不在でも頻繁に高級ミニバンやレンタカーが停まっていて、大きなスーツケースを持った旅行者が出入りしており、民泊行為をしているなら違法である可能性が出てくる。
仮に違法民泊であれば、更なる問題が出てくる。正規ホテル利用なら地域税・雇用を創出するが、違法民泊は課税対象外なので収益があっても絶対に申告されないし、住民票も納税もない“幽霊所有者”が増加すれば所有者不明化し、やがては防災・治安対策が難しくなる。
中国人を引き付けている日本の教育制度
さらに中国人を引き付けている大きな理由は日本の教育制度だろう。中国では受験競争の激しさを背景に、東京大学への中国人留学生の流入が近年急増している。
東京大学の公式集計によると、2024年11月1日時点で中国からの留学生は3545名となっている。これは全留学生4793名中の約70%に相当する。2014年当時は中国人留学生が約1270名だったので10年で3倍近い増加をしたこととなる。
さらに京大では全留学生2942名中、1674名(約57%)、早大では全留学生中5562名中の約3300名(約60%)が、慶應でも全留学生2169名中、約1100名(約50%)が中国人留学生である。それぞれ日本の頂点の大学に、1万近い中国人留学生がいるのだ。
中国国内の大学の難易度や大学院選抜の過酷さから、東大が「賢い抜け道」として魅力的に映るのはごく自然な流れだと思う。さらに東大はMEXT(文部科学省)など奨学金制度・経済面の優位性があるうえ、円安で渡航コストが低く修士選抜制度も多様であるなど、魅力は満載のようだ。
今日の米国の状態から今後の日本像も想像できる。というのも米国では中国系アメリカ人(Chinese Americans)の人口は全米において確かな伸びを示している。
2000年当時は中国系アメリカ人の人口は約260万人だったが、2023年には約500万人と20年でほぼ倍増しているのだ。このうち外国生まれの中国系移民は1700 → 2900万人へと増加していて、アジア系全体の中で中国系は22%を占める最大グループとなっている。