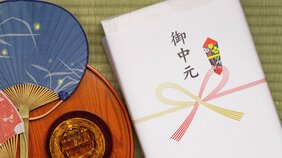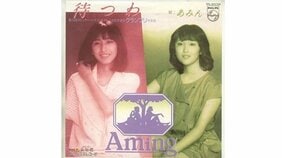コモンで訓練する民主主義のイロハ
李 今回の本のもうひとつのテーマである「コモン(共有財)」について。内田先生はご自分の道場である凱風館を「コモンに」とおっしゃっています。これからのコモンの在り方で大事なのは、「共有する」ことも大事ですけど、それを大企業や国が管理していたら意味がなくて、共有することが「一人ひとりの自治」につながっていくことが必要だと、僕は思っています。
たとえばトクヴィルが「地方自治は民主主義の学校である」と言っていて、今、民主主義と言われて連想するのは、「投票」とかのイメージですけど、とりあえず投票箱に入れたら終わりみたいになっている。日常的に何かを学習するというか、市民が自治について学ぶ場みたいなものが、すっぽり抜け落ちていると思うんです。
内田 そうなんですよね。民主主義って訓練して学習しないと身につかないんです。意見の違う人たちが集まって、対話して、合意形成してゆくためには訓練が要る。その訓練の機会をできるだけ多く提供できるのが民主主義的な国だと思います。
でも、日本の場合は、家庭は民主的ではないし、学校も民主的ではないし、部活もバイトも違う。会社に入っても、もちろんそこは全く民主的な仕組みではない。どこも全部トップダウンの組織なわけですよね。ふつうの子どもには、さまざまな意見を持ち寄って合意形成し訓練する機会を成人するまでに一度もない。
僕は凱風館を「民主的な場」にしたいと思っています。僕は門人たちに「凱風館のためになることだと思うことがあったら、好きにやってください」と言ってあります。僕の許可を取らなくていいから、思うことをやってくれ、と。お金も書生にある程度預けてあって、要ると思うものがあったら、自己判断で買って結構です、と。
さすが高額なものの場合は、僕に言ってもらいますけど、書生が「これ買いましょう」と言ったものについて僕が「ノー」と言ったことは一度もありません。僕は「財布」と同じなんです。「どうやってこの道場を運営していったらいいか」ということについての提言はみんなから伺う。僕はただ言われたことを実践する。
でも、凱風館は「こういう仕組みで運営する」ということを決定したのは僕なんです。誰の意見も聞かないで決めた。「凱風館を民主的な組織にする」ということは僕が非民主的な仕方で決定したんです。僕はこれを「親切な家父長制」と呼んでいるんですけれども、民主制を基礎づけるための「最初の一撃」は必ずしも民主的な手続きを踏んでなされるわけではない。
李 先生は『コモンの再生』(文春文庫)で「身銭を切る」という話をしていて、社会で「自分が一番損している」とみんなが思っているからこそ、身銭を切る大人が必要なのだと。「国家というのは市民が身銭を切って作った人工物であるということになっている」とも。
内田 民主的な組織では、成員たちは決定に参加することができますけれど、同時にリスクを引き受けることもできる。リスクを多くとる人がデシジョン・メイキングにおいてそれだけ大きな発言権を持つことができる。だから、リスクというのは進んで負うものであって、負わされるものではないと僕は思います。