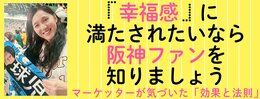「LGBTQの生徒もいて当たり前」
今の学校は基本的に男子・女子を、性別で明確に分けるシステムの上に成り立っています。特に学年が上がれば上がるほど「男子はこっち、女子はこっち」というのがよりハッキリ区分されます。
もちろんそれは生物学的に仕方のないことなのですが、一方で多様性に対する配慮がないと、そのせいで性別違和の子はツラい思いをすることがあります。
ちなみに性別違和というのは、心と体の性が一致しないこと、つまり心は男だけど体は女というようなケースです。一昔前は『性同一性障害』と言われましたが、今では『性別違和』と呼ばれています。
ただ今の時代、さすがにLGBTQについてまったく知らない教師は少ないです。なので、理解があるかどうかは別として、もし生徒から訴えがあれば対応はできると思います。
もし性別違和を訴える生徒がいた場合、担任や保健室の先生が中心になって、対応を検討します。そして、職員会議などで「実は今こういう子がいて、こういう配慮が必要です。こういう声かけはしないようにしましょう」というように、職員の間で共通理解の形成が図られます。
ただし、それは本人や保護者から訴えがあったり、何かトラブルがあったりした場合のみです。そういう話が表に出なければ、そのような子どもはいない前提で教育活動が進んでいきます。
LGBTQが話題になっているとはいえ、まだまだカミングアウトしづらい世の中です。小中高校生が「私はゲイです」とか「私は、体は女だけど心は男です」なんて自分から言うのは、かなりハードルが高いでしょう。
学校の先生方が少しでも「LGBTQの生徒もいて当たり前」というスタンスでいてくれたら、それだけでも心が救われたり、言い出しやすくなったりすると思います。
私のYouTubeの視聴者にも性別違和の子がいて、「プールに入りたくない」「スカートをはきたくない」と相談のDMが来ることがあります。
私が「誰か信頼できる先生がいたら言ってみな、担任の先生じゃなくてもいいから」とアドバイスすると、その子は学年主任に相談したようです。そうしたら、「いいよ、体育の先生に言っといてやるから、プールに入らなくてもいいよ」と言ってもらえたと、喜んでいました。