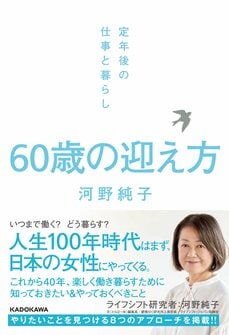自営業なら介護にも対応できる
「雇われない働き方」であれば、長い介護期間にも対応できることを教えてくれたのは、70歳のいまも社会保険労務士として活躍しているM.Mさんです。
M.Mさんは20代後半〜60代の間の多くの時間を、家族の介護と3人の子どもの子育てに費やしてきました。
20代後半に離れて住む父親の介護が始まりました。30代はじめに義父が倒れて介護が必要となり、義祖父・義母との同居を開始。40代は介護も子育ても少し落ち着いたので、この間に自分のやりたいことを模索し、社労士の資格を取得し開業します。
けれども50代で義父の状態が悪化。60代になってからは実母と姉、義兄の介護が始まったため、仕事に費やせる時間は30%ほどだったといいます。
それでも社労士という仕事はM.Mさんにとってようやく手繰り寄せた天職。活動の幅を広げるために始めた研修講師の仕事は時間の自由度がないため手放しましたが、自分の責任と裁量でできる社労士の仕事は大切に続けてきました。
悔いのない介護を終えて70歳を迎えたM.Mさんは、いま時間的な余裕を手にしてあらためて自分のしたいことを広げていこうとしています。
そんなM.Mさんから50〜60代の私たちへのアドバイスは「介護が生じたときには、周囲の助けを積極的に求めること。周りの目を気にすることなく、時には鈍感力を発揮して続けてきた仕事、趣味や楽しみを手放さないこと。それが豊かな将来につながります」ということでした。
生命保険文化センターの調査では平均の介護期間は5年とありますが、M.Mさんのように30 年以上続くこともあります。これまでいつまで続くかわからない介護と仕事の両立は、なかなか答えが見えないテーマだと思っていましたが、「雇われない働き方」を選択することで、ぐんと両立しやすくなることを知り、私はほっとしました。
さらにリモートワークを組み合わせれば、例えば一時的に親の住む地方に移住をしても仕事はできそうです。
どのような形の介護が最適かはそれぞれの家族の事情によりますが、いずれにしても人生は長い。仕事のペースを少し落としても決して手放さずに、まずは悔いのない介護をすることが大事ではないかと思います。
「もっと親にやさしくしてあげたかった」という人にはお会いしますが、介護に費やした時間を後悔しているという人にお会いしたことはありません。
文/河野純子 写真/Shutterstock