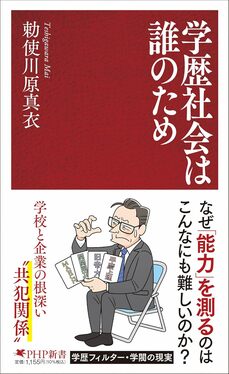「配属先確約」採用は諸刃の剣
ジョブ型に関連して、「初任配属先確約」採用などという言葉も聞きますけど? という方もいらっしゃるかもしれません。どちらも「配属ガチャ」を嘆き、早期退職しかねない若い世代に選ばれる企業であろうとする取り組みと言えます。全国紙を眺めれば、「こっちの企業『ガチャ』ないぞ 志向に合わせ、配属先や勤務地『確約』」みたいな見出しが躍っていることもざらにあります。(朝日新聞デジタル、2024年6月4日)
ただ、しつこくて恐縮なのですが、この「配属先」などをはじめとする、「決まっていないものを決めればいいんですね?」というソリューションには心許なさを覚えます。「決まっていない」ことを問題視し、それを裏返したかのように「決める」(確約する)ソリューションは諸刃の剣と言える点があるのです。
というのも、「決めない」ことで守られる人材の流動性や柔軟性は、雇用者のみならず、被用者側にもあることをこれまで述べてきました。決めると失うものもあるわけです。またその決め方も、学生のうちに自身の適性に合った希望職種や配属先を「決めて」、そのとおりに事が運ぶことが、「いい」のかどうかなんてのは、(あとになってみないと)誰にもわからないという点もあります。はたまた今後、配属確約に「資する」人物とそうでない人物とに分けられていきやしないか? という危うい仮説も頭をもたげるのは私だけでしょうか。
競争から共創へ
「ガチャ」に対する確約策は別の角度から検討しても、やはりしっくりこない議論です。というのは、「そもそも『ガチャ』の不安感の矛先というのは、じつは不確実性そのものに対してではないのではないか?」とも考えられないでしょうか。
「決まっていない」ことが不安だとの主訴はたしかにありますが、そのまま受け取る前に、職場のミクロな環境と労働社会全体のマクロな環境とを行き来して、問題の根っこをつかむ必要がないのか、と私は思います。
そのうえで本当のしんどさは、不確実なことそのものより、配置に「アタリ」「ハズレ」があっても、よりよく働けるチャンスを個人側からはなかなか創出できない点ではないか? とすら思えてきます。言い換えれば、個人の不運を、組織(社会)全体の問題だと思ってもらえず、個人の問題に還流しがちな点こそが辛さなのでは。
うまく仕事を回せるときは、うまく環境にはまっているときです。逆に言えば、相性に恵まれず、ぎくしゃくした不運な状況は誰にでも起こりえます。それをもっと高い精度で予見しろ、「決まっていない」ことが怖いなら「決めちゃおう」というのは迂闊な話です。要するに「ガチャ」論というのは、不確実性を解く方向で考えては筋が悪いのです。
しつこく問いましょう。私たちが気にして、必死で追っているのは、競争のための情報ですか? 共創のための情報ですか? と。
文/勅使川原真衣 写真/shutterstock