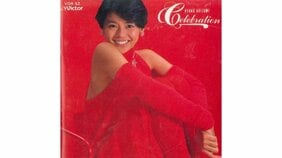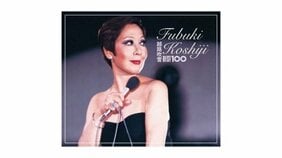国の摂取推奨量は、「壊血病」にならないための数字でしかない
アメリカでは、自分がひょいとガムやキャンディを口に放りこむついでに、「あなたもどう?」というような感じで、ビタミンCの錠剤を勧められる場にたまに出くわす。どれだけ摂っても害がなくからだにいいもの、とみんなが認識している点では、ビタミンCは「安全な食品」扱いだ。
私自身の体験を思い起こせば、はじめにビタミンCと印象的な出会いをしたのは、やはりブームの最中の日本で、25年以上前のことだった。
ビタミンCの摂り方について、ポーリング博士来日時のインタビュー記事*4を読んだとき、なんだかすごく面白そう! とワクワクしたのを覚えている。
アメリカでのビタミンCの1日当たりの摂取推奨量がたったの60ミリグラムだった時代(当時の日本は50ミリグラム*5)に、ポーリング博士は何年間も、ビタミンCのグラム単位での摂取を提唱、実践していた。
85歳当時は、普段、日に18グラム(1万8000ミリグラム)を摂っていたと言う。それは、もっとたくさんのビタミンCを摂れば、病気の予防や治療が効果的にできるのだという理論の発見に基づいた摂取量なのだ。風邪をひきかけたりしたら、さらにもっと量を増やすということらしい。
もともと、国の摂取推奨量というのは、あくまでビタミンC欠乏症である「壊血病」にならないための数字なのだ。
ちなみにビタミンCの別名「アスコルビン酸」は、「壊血病=スコルビュティック(scorbutic)」の前に、それを否定する「a」をつけることから生まれたことばなので、「壊血病防止ビタミン」というわけで、確かに命名の理屈は通っている。
しかし、壊血病というのは死と隣り合わせの病であって、壊血病になるほどビタミンCが不足したら、それは大変な非常事態だということだ。