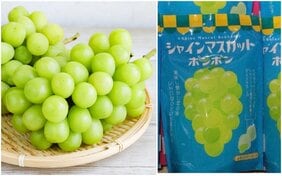場所や時代を超えた、はちみつへの熱い想い
女ミツバチ1匹が一生働いてできあがる美味なひとさじは、大家族を養っていかなければならないハチたちにとって貴重な食料だ。だがそれは私たち人にとっても、味覚の愉しみを超えて、この上なくありがたい恵みである。
日々の体調を整えるのに、寝る前のひとさじがどんなに役立つかを、私自身も体験的に実感するようになって久しい。
はちみつは昔から健康、長寿の鍵とされてきた。
古代エジプトの古文書でも、インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」でも、はちみつは医薬として扱われていて、さまざまな処方が伝えられている。
古代ローマの大博物学者プリニウスの著述の中にも、はちみつを常食する養蜂家がたくさんいる村には、百歳を超える長寿の人がとっても多いというくだりがある。納税台帳の記録によると、なんとローマのその地域(アペニン山脈とポー川の間)には、百歳どころか、135歳以上の人だって、ひとりやふたりではないというのだ*1!
ところ変わって中国の薬学書の中で最も大部で重要なものとされる明朝の『本草綱目』でも、「十二臓腑の病に宜しからずというものなし」と、はちみつは、眼病、皮膚病、呼吸器、消化器なんでもござれ。ほぼ万能薬認定の勢いだ。
まあ、120を超えて生きるとか、万病を治すとか、はちみつのびんを握りしめてそこまで怖れ知らずの野心を掲げようと思わないにしても、現代になって、科学的に成分が分析される結果などを見ていると、歴史上のはちみつ讃歌にも、いろいろうなずける点があるかも、と思えるのもまた確かだろう。
なにしろはちみつは、各種ビタミンやミネラル、酵素、抗酸化物質の宝庫で、真菌や細菌に対する抗菌力もめっぽう強い。明治期に始まった日本薬局方*2にも指定され、今でも薬局方のはちみつというものが医薬品としてちゃんとあるし、それは栄養剤としての他、口内炎や口角炎に効くとされている。
そんな歴史をあれこれ考えたら、はちみつを単なる砂糖代わりの甘味料や嗜好品と思う人が多くなってしまっていた昨今は、人類とはちみつの歴史の中では、もしかすると例外中の例外なのかも、とさえ思えてくる。