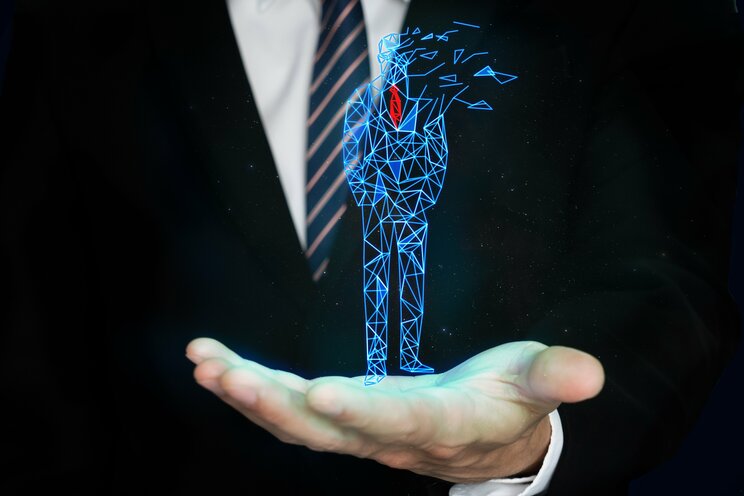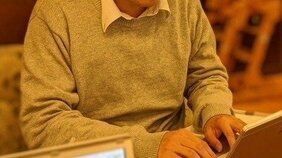鎧をまとっていては成長も貢献もありえない
極めて重要なリーダーのひとりである「教師」たちに、よく言うことがある。それは、心身ともに自分を守らなければならない可能性のある学生に、「家や登下校中に鎧を脱ぐよう指導してはいけない」ということだ。
教師たちにできること、道徳的にやるべきことは、学生がその日1日、あるいは1時間でもいいから、鎧という重圧を脱ぎ捨ててロッカーにしまい、本当の自分を見せられる空間を校内や教室に設けることだ。
学生たちが呼吸をし、好奇心を携えて世界を探検し、息苦しさを感じることなくありのままの自分でいられる空間を、私たちは守らなくてはならない。傷つきやすさと向きあい、心情を吐露できる場所を彼らのためにぜひ確保してほしい。
この研究でわかったのは、たとえひとつでも子どもたちが「鎧を脱げる場所」をもっているなら、その意義を過小評価してはいけないということだ。それはしばしば、彼らの行く末を変えることがある。
人種、階級、性別による差別、あるいは恐怖政治などによって学校、組織、信仰の場、家庭内でさえ鎧が必要なら、そこに誠意ある関係は期待できない。同様に、所属する組織が、非難、恥、皮肉、完璧主義、感情の抑制といった鎧をまとう行動をよしとするなら、革新的な仕事はできないだろう。
鎧をまとっていては、満足な成長も貢献もあり得ない。鎧をもち歩くには大量のエネルギーが必要だし、ときにはそれだけでエネルギーを使い果たしてしまう。
このプロセスをひもとくカギは、「遺伝子に組み込まれていない」行動のリストにある。
先述した3点は、14歳であっても40歳であっても、教えたり、観察したり、計測したりすることが可能である。その証拠に、「勇気は遺伝子によって決まる」と考えていた参加者たちは、このインタビューを受けただけで考え方が変わった。