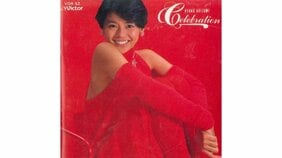農家の高齢化、法改正のダブルパンチで漬物はピンチに
地場野菜を使い、代々受け継がれてきた製法で作られるその土地独自の漬物は、長らく地元住民をはじめ、観光客からも愛されてきた。なかでも、農家が作る漬物の人気は高く、道の駅や直売所などで販売されていることもしばしばだ。
そんな農家の漬物が今ピンチを迎えている。2021年に改正した食品衛生法により、営業専用の調理場、温度付きの冷蔵庫の設置など漬物製造に関する基準が大幅に厳格化してしまったためだ。経過措置が2024年5月末で終了することを機に、6月以降に漬物を製造する農家は対応を迫られている。
農家の多くは、自宅の作業場やキッチンでの製造がメインとなっているが、設備投資には数百万円かかるともいわれており、農業従事者の高齢化も相まって、泣く泣く漬物の製造をやめざるを得ない農家もなかにはいるという。
「道の駅 八王子滝山」は契約農家2戸が販売中止に…
都内唯一の道の駅である東京都八王子市の「道の駅 八王子滝山」は、市内で栽培された野菜はもちろん、農家が作った漬物もいくつか販売されている。大根のしょうゆ漬けやナスのごま油漬け、梅干といったように地場野菜を漬け込んだ農家自慢の漬物が立ち並ぶ。
ところが、漬物を卸す農家のなかでしばらく連絡が来ない方が出てきたと副駅長の須田巧さんは話す。
「八王子滝山では、以前まで5戸の農家さんが作った漬物を販売していたのですが、うち2戸が食品衛生法に触れ、販売中止になってしまいました。残り3戸は、法改正前から設備投資を行い、自前の漬物製造所を整えています。ですが、農家全体の高齢化により漬物の販売数は、年々減少傾向にあるというのが現状です。
当駅に野菜を卸す農家さんのなかには、80代以上の方が圧倒的に多い。そのため廃業を検討する方も少なくなく、仮にあと3~5年で一斉に廃業された場合、農家さん全体の数が30%ぐらい減っていくと思います。
農家さん減少に伴って野菜の生産量が減るにつれて、当然ながら道の駅での漬物の販売数も少なくなる。加えて、今回の法改正が打撃となり、これまでのような漬物のラインナップを維持することは難しくなっていくでしょう」
土地ごとに受け継がれてきたふるさとの味が姿を消していけば、食の多様性は狭まり、我々日本人の食卓のアイデンティティも喪失の機会に見舞われる。まさに今は“漬物クライシス”とでもいうべき状況となっているのだ。