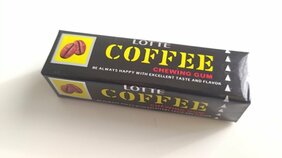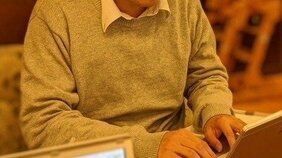内容量減量で実質値上げ…
こうしたなか、ロングセラーのかっぱえびせんも主に2つの課題を抱えている。1つは、冒頭にも触れた「内容量の減量」だ。
物価上昇に伴う原材料の高騰や円安の影響で、実質的な値上げをせざるを得ない状況にあるのは、かっぱえびせんだけではなく、他の商品全体にもいえることである。
塩﨑氏は「外的環境の変化を鑑みつつ、企業努力を重ねながら内容量を決定しているが、かつてのような大容量よりも小分けのアソートタイプの売り上げが伸びていることに目を向けていきたい」と説明する。
「今では多くのお菓子が登場し、味の趣味嗜好も多様化していることから、家族一人ひとりが異なるお菓子を食べるようになってきています。このような背景のなかで、従前のような大容量のものよりも、食べきりサイズのものが求められていると考えています」
もう1つは、消費者にブランドが選ばれる「選好性」だ。
かっぱえびせんの認知率は99%に上り、喫食経験がある消費者も多い。
だが、「食べたことはあるものの、手を取るほどではない」というロングセラーの宿命を、いかに脱却していくかが今後のカギを握るという。

「かっぱえびせんは50代のお客さまがボリュームゾーンになっていて、いわば“かっぱえびせん世代”として、子供のころに食べた記憶や印象がある層になるんです。この世代に向けて、もう一度かっぱえびせんの喫食機会を創出し、ブランドのファンになってもらうことを目標に取り組んでいこうと思っています。先述した『瀬戸の塩と帆立貝柱味』のようなファンとの共創品や、60周年を機にいろんな仕掛けを行っていきたいですね」
取材・文/古田島大介