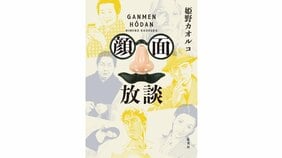ファミリー珍話に寄せて
小学生の頃、国語の作文の宿題で、家族や両親のことをお題にして、“尊敬している”だとか“優しい”などと書いている同級生を見て、「なんたることだ……こんな子どものうちから心にもないことを書いて、教師や目上の人間に媚を売るとは、みんなどうかしている!?」と、真剣に思っていた。
中学生になって、夏休みの読書感想文を太宰治の『斜陽』で提出したところ、我が一族・猫沢家の没落と作品を照らし合わせた、冷酷かつ客観的な批評に、私の心理状態を懸念した担任から呼び出しを食らった。担任は言った。「君の年齢で、こんな主題を選ぶには、まだ早すぎる」。早すぎる? むしろ遅すぎるくらいだ。あの一族で、生き抜く術を見つけ出す分析を始めるのには……!(ハイ、ここでBGM・松任谷由実の《リフレインが叫んでる》どーん!)。
どうしてどうして猫沢家は壊れてしまったのだろう? この命題の追究こそ、子どもが育つには過酷すぎる環境=猫沢家において、私を冷静でいさせてくれた唯一の支えだった……なんて真面目に書くと、『グレート・ギャツビー』みたいな華麗で奇想天外な逸話を想像される方もいるかもしれないが、この物語に出てくるのは、父がカツラだとか、ガス式の風呂がよく爆発するだとか、祖父のマイブームが傍迷惑すぎるとか、そういう取るに足らない珍話だけだ。
そもそも家族という、社会的に「幸福」というイメージを押し付けられた集団の歴史とは、些細な日々の珍話のつらなりだ。そして人さまに聞かせるには恥ずかしい話を往々にして含む。猫沢家はそのパンチがなかなか効いていたため、珍話たちは長らく酒の席での、いい肴だった。それが、50歳を過ぎてからのパリ移住という転機とともに、表舞台に上がることになったというわけだ。
はじめは、「あゝ! なぜ自ら墓穴を掘るような提案をしてしまったのか」と、家族ネタでWEB連載を始めたことを後悔した。私にとっての家族の珍話とは、すでに語り尽くされて新鮮味を失った、過去の遺物でしかなかったから。ところが、連載の3回目頃から、そんな珍話たちを思い出しながら妙に癒されている自分に気づいた。この作用は私個人だけのものではなく、珍話の主人公たちである、今は亡き先代たちもまんざらでもないといった様子で、連載の成り行きを面白がっているんじゃないかと感じたのだ。祖父以外の先代たちは、いずれも目立ちたがり屋の自意識過剰な面々だから、目立つためには己の珍話など喜んで披露するだろう。しかし、私がたびたびここまでバラすか⁉︎という筆のスベりを見せたときは、お得意の怪現象を起こして脅しにかかり、未だこの世とあの世を自由に行き来でもしているかのような無駄な存在感も見せつけてきた。
WEB上での連載最終話《笑いと許しの終末介護》を書いていた今年の春先のこと。おかしな怪現象が続いたある夜、耳元で亡父の「おまえもなんか晒せ」という囁きが聞こえた。それで、別にしなくてもいい私個人の珍話(痔持ちカミングアウト)を披露するに至った。こういうリクエストを無視すると、あとでろくなことがないのは、これまでの経験で学習済みだから……という具合に、亡き両親を含む先代たちと、生きている私とふたりの弟たちの関係性は、生前・死後問わず、一般家庭とはだいぶかけ離れたものだ。
昔から繰り返し聞かれてきた「なぜ、グレなかったのか?」という質問に対しては、世間一般でいうところのグレのメカニズムを考えればすぐに答えが出る。グレるというのは、子どもができる親への最大限の承認欲求表現だ。つまり“グレれば、私のことを見てくれる”という、親の愛への期待ありきで成り立つ手段と言える。残念ながら我が家の大人たちに、こんな普通の手口が通用するはずがないことは、『猫沢家の一族』をお読みになれば、きっとおわかりいただけるだろう。
先代たちが、社会の、時には自然の法則まで逸脱しながら生きて死んだことは、幼い私とふたりの弟たちに、結果、グレるいとまを与えず、ただひたすらに目の前で起こる事象に対する最速での《理解→分析→咀嚼→笑いへの昇華》という修行を課した。その結果、生まれたのがこの『猫沢家の一族』という、ある破天荒で規格外な家族の珍話集である。
外から眺めてどんなにいびつな形をしていようが、なぜかこの家には、互いを認め、許し、笑い飛ばすという愛があった。過去を引きずらないゆえに反省もなく、繰り返される騒動の背景には、父、母という役割への期待も、家族の絆信仰も存在せず、ただ家族という名のバラバラな個の集合体が生きたいまま生きた軌跡が綴られている。
家族という透明な圧からひととき逃れ、ただ笑って読んでいただけたら、猫沢家の数々の珍話も浮かばれることだろう。