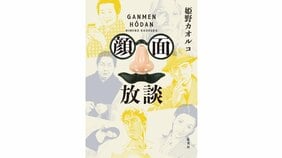斎藤幸平×松本卓也
人々の共有財〈コモン〉の再生から社会が変わる
「時代の閉塞感と社会の分断を乗り越えるために、知の共通基盤=コモン・グラウンドを打ち立てる」をコンセプトにしたビジネス・社会科学・人文書の「集英社シリーズ・コモン」が創刊されました。これを記念して、シリーズ第一弾『コモンの「自治」論』の編者、斎藤幸平さんと松本卓也さんの対談をお送りします。
構成=斎藤哲也/撮影=五十嵐和博
人新世の複合危機に抗するには
松本 斎藤さんと私が編纂した『コモンの「自治」論』が、「集英社シリーズ・コモン」創刊の一冊めとして刊行されることになりました。そこであらためて、なぜ今コモンの「自治」なのかという問題について、斎藤さんと議論できればと思うのですが。
斎藤 現代は「人新世の複合危機」と呼ぶような時代に突入しています。化石燃料を大量に消費する資本主義が発展することで、人間は、地球という人類共通の財産である〈コモン〉を、修復不可能なまでに痛めつけています。その結果、パンデミック、気候変動やインフレ、戦争など、複数のリスクが増幅しあって、私たちの文明や平和、生存を脅かしているわけです。
「人新世」の危機が深まれば、市場は効率的だという新自由主義の楽観的考えは成り立ちません。むしろ、コロナ禍でのロックダウンやワクチン接種計画のように、大きな国家が経済や社会に介入して、私たちの生活を管理する「戦時経済」のような状態になっていくことでしょう。要するに政治がトップダウン型に傾き、全体主義へと接近していくのです。
こうした事態を避けたいなら、トップダウン型とは違う形で、「人新世の複合危機」に対処する道を見いださなければなりません。それが「自治」という道です。
松本 斎藤さんは近年、〈コモン〉の重要性を説き続けてきましたよね。資本主義によって社会の共有財である〈コモン〉が解体されている。ではどうやって〈コモン〉を再生していくのかという問題ですね。
斎藤 たとえば、神宮外苑の再開発なども、〈コモン〉の破壊の典型です。無料か廉価で楽しめる公共性の高いエリアが、再開発によって高層ビルが林立する地区に変わる。それを事業者が一方的にそう決めるのではなく、どういう町にしたいのかを市民が考えるのが自治です。
松本 〈コモン〉と比べると、「自治」は古い言葉です。「自主管理」も同じように古い。でもだからこそ、先人たちのさまざまな実践や運動の歴史につながることができると思うんです。
それをふまえて言うなら、つまり、自治って結局、「場所」ではないでしょうか。多少の流動性はあるけれど、継続的に同じようなメンバーがいて、そこで起こってくるさまざまな問題を自主管理する。自治にはそういう場の継続性という要素が不可欠です。
だからあえて挑発的に「〈コモン〉とは「自治」のことだ」と考えてみたいんです。『コモンの「自治」論』でもさまざまな現場における〈コモン〉が取り上げられています。そこに「自治」という言葉を被せると、場の歴史性や継承性が立ち上がってくる。そういう期待があるんです。
「斜め」の関係の可能性
斎藤 私は松本さんが提起した「斜め」の関係というものが、〈コモン〉や「自治」を考えるうえで非常に重要だと気付かされました。トップダウン型の垂直的な政治に対抗する形で、ウォール街占拠運動のような水平的運動が起こりましたが、水平的な運動って、組織化すること自体を拒絶しがちなんです。
〈コモン〉を自主管理する場合、現場にいて長く経験があり、発言力や統率力もあるような人はやっぱり出てきてしまう。でもその人が、別に絶対的な権力を握らない形で、いろいろな人がリーダーになれる。そういう状態をうまく言い表せなかったんですけど、「斜め」と言うとしっくり来ます。
松本 僕が「斜め」の関係を考えるときの原点にあるのは、障害者運動や当事者研究なんですよね。障害者にとって、同じ障害を持つ仲間とのピアグループがとても重要なんです。グループの中でなら、上から目線の人たちがいる場面では話しにくい本音や感情を表現できますから。
ただ、これだけだと水平的な関係ですが、障害者の運動がユニークなのは、先輩を大事にするんですよ。たとえば車椅子ユーザーにとって、自立生活をすることが課題になる。そのときに、いろんな介助を受けながら、一人暮らしができている人たちはすごいと思われるんです。そしてそういう先輩が一種のロールモデルとなって、自立生活の知恵や方法が仲間に伝達されていくんですね。
あるいは、統合失調症などの精神疾患を抱えた当事者たちの活動拠点になっている「べてるの家」にもユニークなスローガンがあるんです。一般の障害者運動には「自分たちのことを自分たち抜きで決めるな」というスローガンがありますが、べてるの家では「自分のことを自分だけで決めない」なんです。
当事者主権というと、自分の主権を取り返すというふうに考えるのが一般的なんだけど、このスローガンは、自分と同じような経験をしている他者の中で初めて可能になる自分の主権ということを問題にしています。僕はこれが「斜め」だと思っているんですよ。
今の世の中では、主権という言葉を使うと、「結局、自分次第だよね」みたいな「ネオリベ的主体」に絡め取られがちです。だけど、そうじゃない道を教えてくれるのが障害者運動やべてるの家の当事者研究だと思っていて、僕はそういうようなことを「斜め」と言っているんですよ。
斎藤 絶対的な権威に完全に依存するのでもなくて、まるっきり水平にして各人の独立性を強調してしまうのでもない。自立と依存を併存させるような関係ですよね。
効率性を求め過ぎると
レジリエンスを損なう
斎藤 「斜め」の関係は、「集英社シリーズ・コモン」の二冊めとして刊行されるジェレミー・リフキン(経済理論家)の『レジリエンスの時代』に出てくる「ピア政治」という概念にも通底しています。
リフキンは、今までのテクノクラシー的なエリート支配のような政治ではなく、一般の市民たちがガバナンスや立法にもっと関わるような政治のあり方を「ピア政治」と呼んでいるんです。こういったピア政治が、レジリエントな社会をつくっていく上でも重要なんだと。これも一つの「斜め」なあり方ですよね。
同時に、リフキンが今回の本で強調しているのは、効率性を求め過ぎると、社会はレジリエンスを損なうということです。コロナ禍で明らかになったように、半導体を台湾などで集中的に作っていると、台湾に問題が起きれば、世界中の半導体が足りなくなってしまう。つまり、効率性ばかりを求めるとむしろ脆弱さを強めてしまうわけです。
政治も同じだと思います。効率的な意思決定だけを求めるのであれば、トップダウンの独裁でいいという話になってしまう。複合危機の時代にはむしろ、効率性を一定程度抑えていくような取り組みが大事だと、リフキンは言っています。
松本 これからやっぱり、冗長性の価値というものを言っていかなきゃいけないと思います。日本の政治でも、多くの人が国会はいらないと思いつつあるじゃないですか。結論は決まっているんだから、議論はいらない。野党もいらない。でも冗長なこと、まどろっこしいこと、面倒くさいことの価値を回復していくことが自治だと思うんですよ。
ただ「レジリエンス」という言葉も注意が必要です。この言葉は、精神医学の領域でも一時期、流行ったんです。レジリエンスって弾力性だから、ストレスフルなことがやってきたときに、はね返してしまえば病気にならないわけですよね。そこでレジリエンスを高めようという話になるんですが、結局、それが個人の能力として測定されるようになってしまう。つまり、レジリエンスがネオリベ的主体に絡め取られてしまうわけです。
斎藤 リフキンの本で、効率性と対比されるのは「適応」という言葉なんです。その背景にあるのは「自然の再野生化」です。たとえば気候変動を介して、自然がもはや人間がコントロールできないものになっていく。そういう状況では、人間が自然の主人であるという人間例外主義を捨て、自然の一部として、自然とともに生きていかないといけない。だから、ネオリベ的な個人のレジリエントな力で回復していこうという話ではなく、むしろそういう強い主体を諦めて、手放して順応していきましょうというのが、リフキンの言う「レジリエンス」です。
松本 その意味でも、レジリエンスとピアの政治を結びつけて考えるのが大事ですね。
斎藤 現実の政治でも、「斜め」のような転換は起きているんです。その一つの表れが「ミュニシパリズム」(地域主権主義)です。いきなり国政選挙をめざして、国のあり方を変えるのではなく、まずはローカルな自治体を変えていく。こうした潮流は、『コモンの「自治」論』にも執筆している、杉並区長・岸本聡子さんを生んだ市民の運動にもつながっています。これもまた「自治」の実践ですね。
自治が求められるのは政治の場だけではありません。資本主義社会のなかで、労働者としての私たちは自ら「構想」する力を奪われ、資本の命令によって「実行」するだけ。労働の場以外でも、お金に振り回され、資本に魂が包摂されていることに無頓着になっています。「自治」を取り戻すためには、経済の領域で「構想と実行の再統一」を実現して、自主性を取り戻す必要があります。
松本 さまざまな個別のローカルな現場に、自治の可能性があるわけですよね。それぞれの現場でおこなっている自治の事例を外に向けて発信し、それに気付いた人がまた自分の現場で自治をする。『コモンの「自治」論』がそういう自治の連鎖が起きるきっかけになってくれるといいですね。