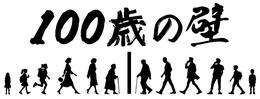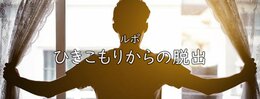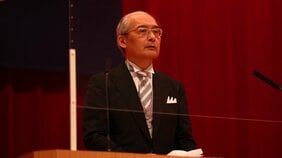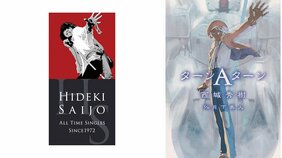卒業時に卒業生の10%が任官辞退、卒業後14年目(38歳)までには50%が退職
防衛省技官となる看護学生の場合、学生の身分は非常勤の特別職国家公務員だ。
制服が貸与され、入学金及び授業料等はかからない。非常勤職員手当が勤務時間(授業を受けた時間)に応じて支給され、年に2回の期末手当(6月、12月)も勤務時間に応じて支給される。通学には交通費が支給され、希望者は有料で寮生活をする。卒業後に防衛省技官となり勤務年限が6年に満たないで離職する場合は、卒業までの経費を償還する義務がある。
防衛医科大学校のいずれの学科も現物支給の給食、宿舎の関係費は「教育訓練を受けた対価にあたる」として徴収しない。中退した学生からも償還金は徴収しないとしている。
防衛医科大学校医学部では卒業時に卒業生の10%が任官辞退し、卒業後9年目(義務期限以前)までに約30%が退職し、卒業後14年目(38歳)までに50%が退職してしまう。
償還金制度は2007年度までは卒業後の年数に応じて金額は大きく減額されたが、以降は年数に応じた金額があまり減らなくなった。それにも関わらず償還金制度は医官の民間への流失を防ぐ役目を果たしていないのが実情だ。
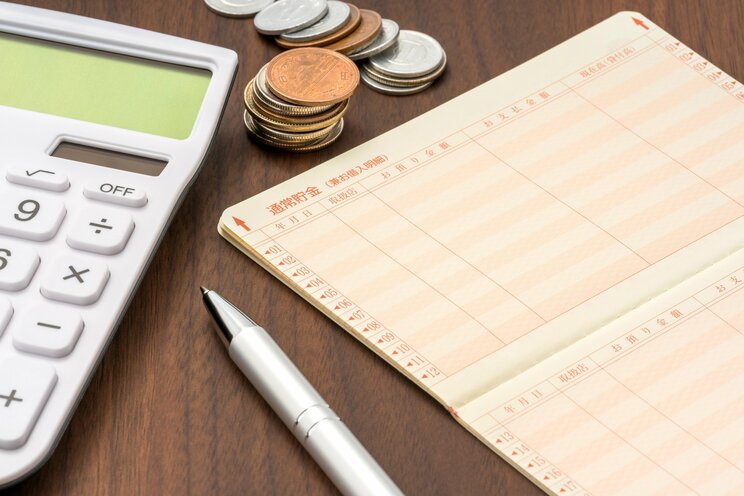
これには、多数の病院が医官を引き抜き(ヘッドハンティング)をしている、昨今の医師不足の影響もある。医師を必要とする病院が国庫返還金の支払いを負担してもいる。
医官が部隊に配属された場合、最大週2日の部外通修(通って研修や教育を受けること)が認められており、協力病院での臨床にて研鑽を積むことができる。通修の日数には部隊長の裁量で幅があり、筆者が所属した第11後方支援連隊衛生隊では週3日間であった。通修先の病院では懇切丁寧に一人前の医師になるように育成しているうちに、自分の病院で働いてほしいと願うようになる。
また、研修を受けている医官も自衛隊病院勤務に戻れば、自衛隊病院勤務では症例が不足しており、臨床経験を十分に積むことは望めない。
一緒に研修を受けている医師たちとの大きな差がついてしまう、医師としてのスキルアップにも不安がある。医官では給与、昇進、技術面での悩みがあるが部外病院の魅力は大きい。こうして医官と部外病院の利害が一致し、研修先病院に引き抜かれることが多い。