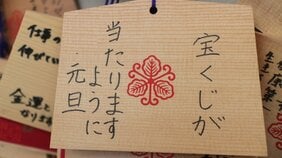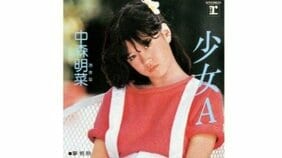気温17℃以下になると「協調遺伝子」にスイッチが入る?
日本人は、「和」を尊重する国民だといわれていますね。「和」とは仲よくすること、協調性が高いことを意味します。
アメリカ・ボストン大学の研究は、「協調性」の高い低いに関係する「協調遺伝子」があると明らかにしました。協調性が高い、やや高い、低い傾向、の3タイプです。
協調性が高い人は、みんなと仲よくやっていける人だと考えると、私たちの仕事の多くは仲間との共同作業だから、協調性の高さも仕事能力や才能のうちですね。陸上競技の100メートル走は協調性なんて関係ありませんが、400メートル・リレーは協調性がカギです。一人ひとりの身体能力で欧米にかなわない日本がサッカーやラグビーで善戦することがあるのは、やっぱり協調性が高いのでしょう。
同じくボストン大学の研究で、興味深いことがわかりました。私たちの身体には、温度によってスイッチが入る温度センサー(TRPA1)があります。これは、ワサビの辛み成分でもスイッチが入ります。そのセンサーの遺伝子タイプによって、協調性のある人とない人が分かれました。
「TRPA1遺伝子」のうち協調性の遺伝子タイプを持つ人は、外気温が17℃以下でスイッチが入り、協調性のある行動をとると推測されます。
どうして17℃なのでしょうか?
ヒトなど霊長類ではまだ不明なことや解明されていないことが多いのですが、外気温が17℃からどんどん下がっていくと、古代なら生命の危機につながりかねません。
だから、人々は身を寄せ合って体温の低下を防いだのでしょう。勝手にふらふら外に出かけていくような協調性に欠けた行動をすれば死んでしまいます。こうして人体の温度センサーと協調性が連動していったのではないか、と私は考えています。
この遺伝子については、ほかにもおもしろいことがわかっています。
先に紹介したクロニンジャー博士のTCIでは、「協調性」は3つある性格のうちの1つでした。ちなみに、残り2つは、「自尊心」「自己超越性」です。
性格の診断をするうえで、「協調性」は重要な要素の1つなんですね。
また別の性格分類に「ビッグファイブ」や「性格5因子」というものがあります。
これは(経験への)開放性・誠実さ・外向性・協調性・神経質傾向(または神経症傾向)の5つ。およその性格はこの5つの組み合わせで説明できます。やや乱暴にいえば、各項目の強中弱(高中低)を調べれば、すべての人は3×3×3×3×3=243とおりある性格類型のどれかに入る、という考え方です。ここでも協調性は性格の基本をなす1つとされています。