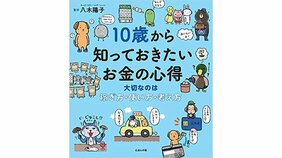小学生から「スマホ」&「AI」と仲良くさせる理由
2022年、OpenAIが生成AI「ChatGPT」を正式に公開したあとは、世界中で爆発的に利用者が広がりました。
その後、Googleが「Gemini」、Microsoftが「Microsoft365 Copilot」、xAIは「Grok」を続々と公開。各社がそれぞれの特性を持たせた生成AIを開発し、さらにそれらを目まぐるしくバージョンアップさせながら、ものすごいスピードで可能なことが増えています。そして、最新のスマホには、それらのAIが最初から搭載されています。
少し前に言われていた、誰もが手のひらでAIを駆使できるようになると言われていた未来は、今、まさに現実となりつつあります。
でも、ワクワクする未来がすぐそこにある一方で、一部の親たちは、こんな不安も抱えているようです。
「AIにレポートや宿題を丸投げしちゃうんじゃないか」
「試験中にカンニング目的で使われたら困る……」
そんな“悪用リスク”への心配の声も、たしかに多く聞こえてきます。
でも、世界全体がすでに動き出しているこの流れを、止めることも、避けることも、もはや不可能です。むしろ、ここから目を背けてしまうことこそ、子どもたちにとって一番のリスク。世界のスピードに、取り残される未来が待っているかもしれないからです。
だったら、AIを「どう使うか?」を前向きに考えるほうが、よっぽど健全なリスクの取り方だと私は思います。
「AIに仕事が奪われる」という話はもう珍しくありません。でも、それを“いつか来る未来”ではなく、“もう始まっている現実”として受け止めないと、私たち人間が置いていかれるのは時間の問題です。
とはいえ、必要以上に不安になることはありません。調べもの、計算、文章作成など、時間を短縮してAIが肩代わりしてくれることは増えています。
だからこそ、「努力して全部自分でできるようにならなきゃ」と思い込む必要は、もうないのかもしれません。今の時代に必要なのは、“全部できる人”になることじゃなく、“うまく使える人”になること。