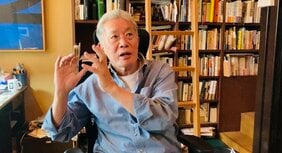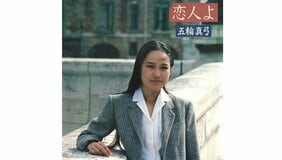「速い思考」と「遅い思考」
人間のアテンションに対する最適化は、人間がもつ心理特性と重なり合うことで、ときにより複雑で厄介な問題にもつながる。
ここでは、心理学の分野でしばしば参照される「二重過程理論」という理論モデル(あくまで仮説的なモデルであり、実際の脳の機能はもっと複雑なものとされる)を確認しておこう。
心理学者・行動経済学者のダニエル・カーネマンは、人間の2つの思考過程を「速い思考」と「遅い思考」と分類し、「速い思考」を実現する脳のシステムを「システム1」、「遅い思考」を実現する脳のシステムを「システム2」とよんで区別している*1。
システム1の「速い思考」とは、自動的・直観的にすばやく判断する思考モードのことを指す。たとえば、突然聞こえた音の方角を感知して、特に意識することなく自然とアテンションを向けてしまうようなプロセスが「速い思考」で、いわば意識的なコントロールがおよぶ前の「反応」などが含まれる。
一方の「遅い思考」とは、複雑な計算のように意識的に時間をかけて論理的な推論などを行う思考モードのことで、たとえば聞こえた声の内容を言語的に判断して、その真偽を吟味して確かめるようなことを指す。
実際はこのシステム1(「速い思考」)とシステム2(「遅い思考」)は連携して処理をするが、システム1が自動的にアテンションの対象を振り分ける(音が聞こえた方角に気づかせる)のに対し、システム2はその対象にどのように対処すべきかを意識的に判断する(聞こえた音にどのように応答するかを考える)というような過程をたどる。
この「二重過程理論」を含む人間の情報処理過程にはさまざまな理論があるが、システム1のような認知資源の節約につながる情報処理方略のことを「ヒューリスティック」とよぶ。
ヒューリスティックは直観や経験則に基づいて、すばやい判断を行う思考様式で、たとえば「(ちゃんとした根拠はないが)パッとみた目が外国人にみえるから日本語が通じないだろうと判断する」といった「短絡的な」判断のことを指す。