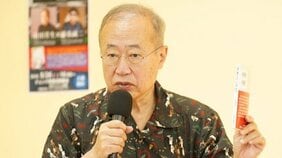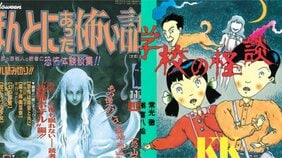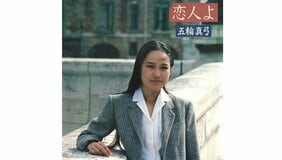この記事は会員限定記事(無料) です
続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
この記事のまとめ
- #1「新聞は分かりにくくて読む気にならない」「長文が苦痛」Z世代にネット記事を読んでもらうために必要なテクニック
- #2「絶賛」「SNSで称賛相次ぐ」読者を騙す悪質なネットニュースの釣り見出し…良い記事に本当に必要なのは「自分事となるストーリー」
- #3記事が読まれるかどうかは見出しで決まるって本当?「47NEWS」の部長が教える「読まれる見出し」4原則
- #4「マスゴミ」「オールドメディア」毛嫌いされている既存メディアがそれでも存在しなければならない理由
次のページ
画像ギャラリー
関連記事
-
-
-
なぜ人は霊感商法にダマされるのか? 高額な壺を買えば悩みが解決すると思い込ませる巧妙な手口イマジナリー・ネガティブ #1
-
-
-