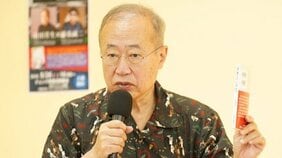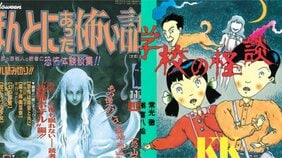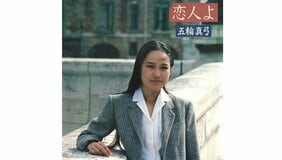最後の課題「見出し」
新聞とデジタル記事とでは、見出しの付け方は明確に異なる。
新聞は、すでに新聞を手に取っている読者に向けて、記事のエッセンスであるリードの、さらにエッセンスを見出しにする。一方で、デジタル向けではプラットフォームに並ぶ無数の記事の中から、自分が書いた記事を何とか選んでもらえるような見出しの付け方をしている。簡単に言えば、競争があるかないかの違いとも言える。
ただ、選んでもらえるなら何でもいいわけではなく、いわゆる「釣り見出し」にならないよう注意する必要がある。
読者の目を引くことを第一目的にすると、どうしても大げさな表現を使いたくなる。その結果として、記事に書いていない内容を見出しに取りがちになる。結果的にその記事単体では多く読まれたとしても、次第に読者が引っかからなくなる。